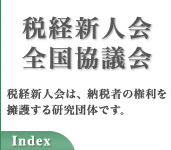所得税法第56条(以下、所法56条とする)の解釈をめぐって、近年相次ぐ裁判例や裁決例があり、多くの税法学者、税理士等実務家が雑誌等で論文を発表しているので、改めて研究ということにはならないと思われるが、今ひとたび整理をしてみる必要はあると考えられる。 所得税法第56条(以下、所法56条とする)の解釈をめぐって、近年相次ぐ裁判例や裁決例があり、多くの税法学者、税理士等実務家が雑誌等で論文を発表しているので、改めて研究ということにはならないと思われるが、今ひとたび整理をしてみる必要はあると考えられる。

 まず、近年の独立した事業を営む夫婦間の営業報酬の支払について、必要経費として認められるかを争点とした事例から検討する。 まず、近年の独立した事業を営む夫婦間の営業報酬の支払について、必要経費として認められるかを争点とした事例から検討する。 |
| (1) |
生計を一にする妻に支払った弁護士報 酬の必要経費性の判例・・・H15.06.27 東京地裁、H15.10.15 東京高裁、H16.11.02 最高裁(以下、妻弁護士事件という) |
| (2) |
生計を一にする妻に支払った税理士報酬の必要経費性の判例・・・H15.7.16 東京地裁、H16.06.09 東京高裁(以下、妻税理士事件という) |
 |
第1節 妻弁護士事件 妻弁護士事件 |
 原告である夫は、弁護士事務所を営んでいる。その妻は、夫とは別の弁護士会に所属し、事務所も別に開設して弁護士業務を営んでいる。会計も夫とは別であるなど、事業としては夫から独立しているが、生活面では同居しているなど、「生計を一にしている」状況である。 原告である夫は、弁護士事務所を営んでいる。その妻は、夫とは別の弁護士会に所属し、事務所も別に開設して弁護士業務を営んでいる。会計も夫とは別であるなど、事業としては夫から独立しているが、生活面では同居しているなど、「生計を一にしている」状況である。

 原告は営む業務の一部を妻に行わせ、その業務の対価として弁護士報酬を妻に支払い、必要経費として確定申告したところ、税務署長より更正処分及び過少申告加算税処分を受けた。最高裁の判決がでるまでの経緯を略述すると下記のとおりである。 原告は営む業務の一部を妻に行わせ、その業務の対価として弁護士報酬を妻に支払い、必要経費として確定申告したところ、税務署長より更正処分及び過少申告加算税処分を受けた。最高裁の判決がでるまでの経緯を略述すると下記のとおりである。 |
| ・ |
平成9年〜11年分の確定申告において、夫は妻への弁護士報酬の支払を必要経費として計上 |
| ・ |
更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分 |
| ・ |
審査請求 |
| ・ |
国税不服審判所は、主張は認められないとして裁決(一部取消) |
| ・ |
処分取り消しを求めて訴訟 |
| ・ |
所法56条の適用ありの判決(H15東京地裁)
  支払いの対象者、 支払いの対象者、
  支払の事由が合致している、として 支払の事由が合致している、として |
| ・ |
更正処分取消等請求控訴事件(H15東京高裁)
  の要件が適用されない合理的事情は存しない、として棄却 の要件が適用されない合理的事情は存しない、として棄却 |
| ・ |
更正処分取消等請求事件(H16最高裁)
生計を一にする親族が居住者と別に事業を営む場合であっても、そのことを理由に所法56条の適用を否定することはできない、として棄却 |

 この経緯のなかで争点となったのは所法56条の適用如何であり、その要件は二つに集約される。 この経緯のなかで争点となったのは所法56条の適用如何であり、その要件は二つに集約される。
 |

 |
支払の対象者が「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族」に該当するか。 |

 |
「その居住者の営む不動産所得、事業所得、又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合」に相当するかどうか。 |

 地裁の判示によれば、「その者の営む事業の形態がいかなるものか、事業から対価の支払を受けるその者の親族がその事業に従属的に従事しているか否か、対価の支払はどのような事由によりされたのか、対価の額が妥当なものであるのか否かなどといった個別の事情によって、同条の適用が左右されることをうかがわせる定めは、同条及び同法の他の条項に全く存在しない。したがって、前記の二つの要件が備わっている限り、このような個別の事情のいかんにかかわりなく、同条が適用されると解すべきである。」として、原告の訴えを斥けている。 地裁の判示によれば、「その者の営む事業の形態がいかなるものか、事業から対価の支払を受けるその者の親族がその事業に従属的に従事しているか否か、対価の支払はどのような事由によりされたのか、対価の額が妥当なものであるのか否かなどといった個別の事情によって、同条の適用が左右されることをうかがわせる定めは、同条及び同法の他の条項に全く存在しない。したがって、前記の二つの要件が備わっている限り、このような個別の事情のいかんにかかわりなく、同条が適用されると解すべきである。」として、原告の訴えを斥けている。

 このことは、従来からの伝統的解釈に従ったものと言える。また、憲法14条1項に違反するのでは、という憲法論議については、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるをえないものというべきである。」として消極的な姿勢を示している。 このことは、従来からの伝統的解釈に従ったものと言える。また、憲法14条1項に違反するのでは、という憲法論議については、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるをえないものというべきである。」として消極的な姿勢を示している。 |
 |
 「生計を一にする」という文言の初出は、旧所得税法8条(昭和22年3月31日法律第27号)であるとされる。 「生計を一にする」という文言の初出は、旧所得税法8条(昭和22年3月31日法律第27号)であるとされる。

 「第8条 「第8条 この法律において同居親族とは、配偶者及び3親等以内の親族で生計を一にする者をいう。前項の規定の適用については、生計を一にする者の1人と同項に規定する関係ある者が2人以上あるときは、その2人以上の者相互の間には同項に規定する関係がない場合においても、その生計を一にする者全部の間に同項に規定する関係があるものとみなす。この法律において扶養親族とは、納税義務者の同居親族のうち配偶者及び年齢19歳未満若しくは61歳以上又は不具廃疾の者(命令で定める者を除く。)をいう。」 この法律において同居親族とは、配偶者及び3親等以内の親族で生計を一にする者をいう。前項の規定の適用については、生計を一にする者の1人と同項に規定する関係ある者が2人以上あるときは、その2人以上の者相互の間には同項に規定する関係がない場合においても、その生計を一にする者全部の間に同項に規定する関係があるものとみなす。この法律において扶養親族とは、納税義務者の同居親族のうち配偶者及び年齢19歳未満若しくは61歳以上又は不具廃疾の者(命令で定める者を除く。)をいう。」

 また、同条に関する旧通達(昭26年 また、同条に関する旧通達(昭26年 所基通50)の内容は以下のとおりである。 所基通50)の内容は以下のとおりである。

 「『生計を一にする』とは有無相扶けて日常生活の資を共通にしていることをいうのであるから、次の諸点に留意する。 「『生計を一にする』とは有無相扶けて日常生活の資を共通にしていることをいうのであるから、次の諸点に留意する。
 |
| 一 |
 公務員、会社員等が勤務の都合上妻子等と別居し、または就学、療養中の子弟等と起居をともにしていないような場合においても、常に生活費、学費金、または医療費等を送金して扶養しているときは、生計を一にするものとする。 公務員、会社員等が勤務の都合上妻子等と別居し、または就学、療養中の子弟等と起居をともにしていないような場合においても、常に生活費、学費金、または医療費等を送金して扶養しているときは、生計を一にするものとする。 |
| 二 |
 同一の家屋に起居する親族であっても互いに相独立し、日常生活の資を共通にしていない場合は、生計を一にしないものとする。」 同一の家屋に起居する親族であっても互いに相独立し、日常生活の資を共通にしていない場合は、生計を一にしないものとする。」
 |
 これに対して、現行の定義である「所得税基本通達2−47」は次のようになっている。 これに対して、現行の定義である「所得税基本通達2−47」は次のようになっている。

 「法に規定する『生計を一にする』とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 「法に規定する『生計を一にする』とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
 |
| (1) |
勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 |
 |
イ |
当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 |
 |
ロ |
これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
 |
| (2) |
 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。」 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。」
 |
 「生計を一にする」とは、旧通達の「有無相扶けて日常生活の資を共通にしている」という文言が外れるとともに、「必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではない」として、その範囲が拡大されている。 「生計を一にする」とは、旧通達の「有無相扶けて日常生活の資を共通にしている」という文言が外れるとともに、「必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではない」として、その範囲が拡大されている。

 そして同居の場合除外されるのは、「互いに独立した生活」を営んでいる場合のみとされ、しかも「明らかに・・・・・・認められる」という文言が入ったことで、客観性を求められるとともに、その事実認定はまずは課税庁に委ねられたともいえる。 そして同居の場合除外されるのは、「互いに独立した生活」を営んでいる場合のみとされ、しかも「明らかに・・・・・・認められる」という文言が入ったことで、客観性を求められるとともに、その事実認定はまずは課税庁に委ねられたともいえる。

 前記のとおり、法令上「生計を一にする」という文言は頻出している。これを要件として大別すると二つとなる。一つは納税者にとって有利なものとなる要件であり、各種所得控除の適用要件となるものにみられる(所法72、同73その他)。もう一つは納税者にとって不利なものとなる要件であり、所第56条のように、給与等の必要経費算入が否認される場合である。 前記のとおり、法令上「生計を一にする」という文言は頻出している。これを要件として大別すると二つとなる。一つは納税者にとって有利なものとなる要件であり、各種所得控除の適用要件となるものにみられる(所法72、同73その他)。もう一つは納税者にとって不利なものとなる要件であり、所第56条のように、給与等の必要経費算入が否認される場合である。

 前者については、「生計を一にする」ということを広く解釈したほうが納税者にとって有利となり、また法の趣旨にも適うものであるが、後者の場合は逆となる。そもそも「生計を一にする」という言葉が旧通達で使用されたのは控除対象配偶者等の定義のためであり、この言葉を広く解する傾向にあるのはやむを得ないものと考えられる。 前者については、「生計を一にする」ということを広く解釈したほうが納税者にとって有利となり、また法の趣旨にも適うものであるが、後者の場合は逆となる。そもそも「生計を一にする」という言葉が旧通達で使用されたのは控除対象配偶者等の定義のためであり、この言葉を広く解する傾向にあるのはやむを得ないものと考えられる。 |