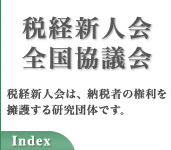
| > 生活保護の基本的視点 > 改憲論の現状と問題点 > 情報公開請求から税理士試験制度を考える(上) |
| 次の税理士法改正は如何にあるべきか |
| 東京税経新人会 制度特別委員会 |
| 1.はじめに 2.次期税理士法改正にむけた議論がはじまる 3.憲法の理念にそった税理士法の改正が求められる |
| 「確定申告の際、申告者が作成した決算書の数字を税務ソフトに入力するといった手伝いをしただけで民主商工会の女性事務局員(禰屋さん)が脱税がらみの「法人税法違反」等で逮捕・起訴され、しかも当の申告者が逮捕も勾留もされていないのに、なんと1年2ヵ月間(428日)も勾留される。こんな異様な事件が岡山地裁で審理中だ。・・・・・・しかも、この種の経済事件とはまったく管轄外のはずの岡山県警公安部は翌2014年1月21日、禰屋さんを『法人税法違反』で逮捕したのに続き、2月には『税理士法違反』で再逮捕。だが、脱税当事者であるはずの建設会社社長夫婦は後に在宅のまま懲役1年6ヶ月・執行猶予付の有罪判決が確定したものの、1日も勾留されず、なぜか広島国税局の捜索すら受けていない。 ・・・一方、建設会社の確定申告業務には何も関与していなかった倉敷民商事務局長の小原淳氏と事務局次長の須増和悦氏の二人も、14年2月に『民商会員が確定申告書の作成・提出に際して、税理士でもないのに会員自身が作成した決算書の数字を、税務ソフトに入力するなどの実務応援をした』として『税理士法違反容疑』で逮捕された。」(週刊金曜日2016年1月19日号) |
4.戦前における税務代理士法の成立とその背景 5.アメリカ占領下における税理士法の成立 参考資料( 税経新人会全国協議会第20回全国研究集会記念誌) (昭和39年「改正」法案に至る経緯と税理士法改正に関する基本要綱成案まで・唐木田明雄氏) |
| 税務代理士法が廃止され、代わって税理士法が制定された。敗戦に伴う国家体制の変革に連動したものであったが、資格取得が許可制から試験制度に、また強制加入の特別法人組織が入退会の自由な社団法人に改組されたにとどまり、税務代理士法上の取締法的体系は現代法に受継がれた。既に新憲法は制定され、旧来の法律や制度の改廃著しい当時にあって、不思議なほどその影響の少ない変革であった。 |
| 6.税務代理士法と税理士法の共通点と相違点 (1)税理士の使命 (2)税理士の業務 (3)税理士(税務代理士)の資格者と税理士(税務代理士) (4)税理士業務の制限、名称の使用制限(業務独占について) (5)脱税相談の禁止、助言義務規定、帳簿作成の義務などについて (6)主務大臣等による税理士、税理士会の監督等 (7)罰則について 7.税理士法改正の視点 (1)税理士の使命について (2)税理士の業務について (3)税理士業務の制限、名称の使用制限(業務独占について)について (4)脱税相談の禁止、助言義務規定、帳簿作成の義務などについて (5)税理士業務の制限、名称の使用制限(業務独占について) 「税理士法制定時においては一定の有資格者を確保するため政策的に既存の国家資格者である弁護士及び公認会計士を税理士の有資格者とした経緯はあるが、現在の税理士登録者数を考えてみると税理士法第3条において弁護士、公認会計士に無条件に資格を付与することについては、合理的な理由は見いだせない。」(2014年3月制定の税理士法改定時における全国協議会の意見)。 (6)税理士・税理士会の自治について (7)罰則について (8)他の項目及び税理士・税理士会の社会公共性について |
| (以上) |
| ▲上に戻る |