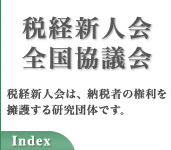はじめに

 この5月3日で日本国憲法は施行69年を迎えた。今年の11月3日は、その制定70周年である。この「節目」の年に際して、日本国憲法とりわけ9条は、いつにもまして人々の関心を集めている。現在、新学期が始まったところだが、私が出講している非常勤先の大学(経済学部)の憲法の授業(選択科目)は、例年のほぼ2倍の受講生が集まった。そんなところにも憲法への「関心の高まり」を実感している。高校生を含む若者、幼子(おさなご)の子育て世代による憲法問題への積極的発言も目立ってきた。憲法を講じて30年近くなろうとする者としては嬉しい限りである。 この5月3日で日本国憲法は施行69年を迎えた。今年の11月3日は、その制定70周年である。この「節目」の年に際して、日本国憲法とりわけ9条は、いつにもまして人々の関心を集めている。現在、新学期が始まったところだが、私が出講している非常勤先の大学(経済学部)の憲法の授業(選択科目)は、例年のほぼ2倍の受講生が集まった。そんなところにも憲法への「関心の高まり」を実感している。高校生を含む若者、幼子(おさなご)の子育て世代による憲法問題への積極的発言も目立ってきた。憲法を講じて30年近くなろうとする者としては嬉しい限りである。

 こうした状況の背景にあるもの、それは、2014年7月の閣議決定から昨年9月の安保関連法(以後、戦争法と呼ぶ)の強行採決にいたる一連の事態であり、これに対して「憲法9条・平和主義を守れ」という声に加えて、「立憲主義を壊すな」、「民主主義を取り戻そう」などの声が唱和されて、1960年の「60年安保」を彷彿(ほうふつ)とさせる反対運動が盛り上がったことであることは疑うべくもなかろう。 こうした状況の背景にあるもの、それは、2014年7月の閣議決定から昨年9月の安保関連法(以後、戦争法と呼ぶ)の強行採決にいたる一連の事態であり、これに対して「憲法9条・平和主義を守れ」という声に加えて、「立憲主義を壊すな」、「民主主義を取り戻そう」などの声が唱和されて、1960年の「60年安保」を彷彿(ほうふつ)とさせる反対運動が盛り上がったことであることは疑うべくもなかろう。

 「60年安保」の際には、安保条約の改定が強行された直後には、反対運動の側に「喪失感」、「虚脱感」が生じ、全体のムードが「政治の季節」から「経済成長(所得倍増)」へと変動していったそうだが、「(20)15年安保(法制)」の後は、きびすを接して「戦争法は廃止!」を唱える運動が即座に始まり、参議院での強行採決当日の日本共産党による「戦争法廃止の国民連合政権を」という提起に呼応した市民運動(安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合)が立ち上げられた。 「60年安保」の際には、安保条約の改定が強行された直後には、反対運動の側に「喪失感」、「虚脱感」が生じ、全体のムードが「政治の季節」から「経済成長(所得倍増)」へと変動していったそうだが、「(20)15年安保(法制)」の後は、きびすを接して「戦争法は廃止!」を唱える運動が即座に始まり、参議院での強行採決当日の日本共産党による「戦争法廃止の国民連合政権を」という提起に呼応した市民運動(安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合)が立ち上げられた。

 こうした運動のパワーに支えられて、2016年2月19日には、日本共産党、民主党、社会民主党、維新の党、生活の党と山本太郎となかまたちの野党5党(その後維新の党の一部議員は民主党に合流・合併し、民進党を結成)によって「戦争法廃止法案」が衆議院に提出されるとともに、参議院選挙や衆議院の補欠選挙で野党による選挙協力も進められるという画期的な動きになっている。4月24日の衆院補選(北海道5区)では、敗れはしたものの、野党統一候補が自民の候補に肉薄した。 こうした運動のパワーに支えられて、2016年2月19日には、日本共産党、民主党、社会民主党、維新の党、生活の党と山本太郎となかまたちの野党5党(その後維新の党の一部議員は民主党に合流・合併し、民進党を結成)によって「戦争法廃止法案」が衆議院に提出されるとともに、参議院選挙や衆議院の補欠選挙で野党による選挙協力も進められるという画期的な動きになっている。4月24日の衆院補選(北海道5区)では、敗れはしたものの、野党統一候補が自民の候補に肉薄した。

 本稿では、こうして戦争法を廃止して憲法9条を守り抜き、その実現をはかることの意義について論じてみたい。 本稿では、こうして戦争法を廃止して憲法9条を守り抜き、その実現をはかることの意義について論じてみたい。 |
 |
1. 戦争法の問題点

 まず、戦争法の主な問題点について整理をしておこう。私は、それは大きく分けて「4つのパーツ」として整理できると考えている。 まず、戦争法の主な問題点について整理をしておこう。私は、それは大きく分けて「4つのパーツ」として整理できると考えている。

 第一は、集団的自衛権の行使容認である。 第一は、集団的自衛権の行使容認である。
 今回の自衛隊法と武力攻撃事態法の改正により、「存立危機事態」における自衛隊による武力の行使が規定された。これは、「憲法9条の下では個別的自衛権の行使のみが許され、集団的自衛権の行使は許されない」いう60年以上にわたって政府が維持してきた解釈を変更して、 今回の自衛隊法と武力攻撃事態法の改正により、「存立危機事態」における自衛隊による武力の行使が規定された。これは、「憲法9条の下では個別的自衛権の行使のみが許され、集団的自衛権の行使は許されない」いう60年以上にわたって政府が維持してきた解釈を変更して、 我が国と密接な関係にある他国への攻撃により、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある、 我が国と密接な関係にある他国への攻撃により、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある、 その危険を排除するために他に適当な手段がない、 その危険を排除するために他に適当な手段がない、 必要最小限度の実力行使という3要件の下で、集団的自衛権の行使をも認めようというものである。しかし、ここでの「我が国と密接な関係にある他国」は、米国に限定されていない。 必要最小限度の実力行使という3要件の下で、集団的自衛権の行使をも認めようというものである。しかし、ここでの「我が国と密接な関係にある他国」は、米国に限定されていない。

また、「存立危機武力攻撃」(武力攻撃事態法2条8号ハ(1))とは、どのような武力攻撃のことなのか、何を基準にして、「他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要」(同法9条2項1号ロ)と認めるのかなどが、あいまいである。そして、この攻撃を「排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使」が、どの程度のものであれば「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」(同法3条4項)にとどまるのかなど、使われている概念が極めて漠然としており、その範囲は不明確である。その結果、「存立危機事態」対処は、歯止めのない集団的自衛権行使につながりかねない。

 第二は、他国の軍隊の武力行使への「後方支援」(Logistic support)の一挙拡大である。 第二は、他国の軍隊の武力行使への「後方支援」(Logistic support)の一挙拡大である。
 従来の周辺事態法を名称変更した重要影響事態法における「後方支援活動」と新設の国際平和支援法における「協力支援活動」は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるが、これらは、活動領域について地理的な限定がなく、「現に戦闘行為が行われている現場」以外のどこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた「弾薬の提供」や「発進準備中の戦闘機への給油」も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されている。 従来の周辺事態法を名称変更した重要影響事態法における「後方支援活動」と新設の国際平和支援法における「協力支援活動」は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるが、これらは、活動領域について地理的な限定がなく、「現に戦闘行為が行われている現場」以外のどこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた「弾薬の提供」や「発進準備中の戦闘機への給油」も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されている。

これは、もはや「外国の武力行使とは一体化しない」といういわゆる「一体化」論がおよそ成立しないことを意味するものである。したがって、そこでの自衛隊の支援活動は「武力の行使」に該当し憲法9条1項に違反するものである。なお、こうした「後方支援」であれば、「外国の武力行使とは一体化しない」という理屈は、国際的には通用しない日本独特のものであり、「後方支援」であっても歴とした武力行使の一環として、集団的自衛権行使に該当しうることもわきまえておかねばならない。

 第三は、外国軍の武器等防護のための武器使用である。 第三は、外国軍の武器等防護のための武器使用である。
 改正自衛隊法は、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」米軍等の武器等防護のために自衛隊に武器の使用を認める規定を盛り込んだ。この規定の前にある自衛隊法95条は、もともと保管されている武器等についての規定のはずである。しかし、改正法95条の2は、米軍等の武器等防護というまったく性格の異なるものにまで引き及ぼしてしまった。この規定は、自衛隊が米軍等と警戒監視活動や軍事演習などで平時から事実上の「同盟軍」的な行動をとることを想定している。このような活動は、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発しかねない。そして、武器の使用という形をとって武力の行使にまでエスカレートする危険をはらんでいる。その危険は、南シナ海での中国の海洋島建設、それに対するアメリカの「航行の自由」作戦とそれへの日本の参画によって現実のものになろうとしている。 改正自衛隊法は、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」米軍等の武器等防護のために自衛隊に武器の使用を認める規定を盛り込んだ。この規定の前にある自衛隊法95条は、もともと保管されている武器等についての規定のはずである。しかし、改正法95条の2は、米軍等の武器等防護というまったく性格の異なるものにまで引き及ぼしてしまった。この規定は、自衛隊が米軍等と警戒監視活動や軍事演習などで平時から事実上の「同盟軍」的な行動をとることを想定している。このような活動は、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発しかねない。そして、武器の使用という形をとって武力の行使にまでエスカレートする危険をはらんでいる。その危険は、南シナ海での中国の海洋島建設、それに対するアメリカの「航行の自由」作戦とそれへの日本の参画によって現実のものになろうとしている。

 第四は、PKO 活動などにおける自衛隊の活動、業務の拡大と武器使用の強化である。 第四は、PKO 活動などにおける自衛隊の活動、業務の拡大と武器使用の強化である。
 改正国際平和協力法は、協力対象に従来のPKO 活動などに加えて、国連が統括しない人道復興支援・安全確保活動も含めることにした。また、安全確保業務、統治組織の設立・再建援助業務、司令部業務、「駆け付け警護」を追加し、任務遂行型の武器使用や「駆け付け警護」のための武器使用もできるようにした。これによって自衛隊は、「有志連合」型の軍事活動における治安活動(という名目での掃討作戦)などにも参加できるようになり、またPKO 活動の際にもより危険でなおかつ民間人を戦闘に巻き込むおそれのある業務に携わることになる。 改正国際平和協力法は、協力対象に従来のPKO 活動などに加えて、国連が統括しない人道復興支援・安全確保活動も含めることにした。また、安全確保業務、統治組織の設立・再建援助業務、司令部業務、「駆け付け警護」を追加し、任務遂行型の武器使用や「駆け付け警護」のための武器使用もできるようにした。これによって自衛隊は、「有志連合」型の軍事活動における治安活動(という名目での掃討作戦)などにも参加できるようになり、またPKO 活動の際にもより危険でなおかつ民間人を戦闘に巻き込むおそれのある業務に携わることになる。

 総じて、今回の戦争法によって、自衛隊の軍事的役割は、格段に拡張されている。とくに重要影響事態法や国際平和支援法にもとづく「後方支援」は、両方を合わせると、「支援が不可能」というケースを見つけることが困難なくらいに広範囲をカバーしており、随意に他国の軍事行動に「後方支援」(という名の武力行使への参加)が可能となる仕組みである。「海外で戦争をしない」という曲りなりにも戦後守られてきた原則がここから破られる危険が大きい。武力行使を含む集団的自衛権行使を想定する「存立危機事態」は、アメリカなどが武力攻撃された場合(たとえば9・11のようなケース)であり、憲法9条の重大な侵害であるが、それでも頻繁に起こることは想定しがたい。 総じて、今回の戦争法によって、自衛隊の軍事的役割は、格段に拡張されている。とくに重要影響事態法や国際平和支援法にもとづく「後方支援」は、両方を合わせると、「支援が不可能」というケースを見つけることが困難なくらいに広範囲をカバーしており、随意に他国の軍事行動に「後方支援」(という名の武力行使への参加)が可能となる仕組みである。「海外で戦争をしない」という曲りなりにも戦後守られてきた原則がここから破られる危険が大きい。武力行使を含む集団的自衛権行使を想定する「存立危機事態」は、アメリカなどが武力攻撃された場合(たとえば9・11のようなケース)であり、憲法9条の重大な侵害であるが、それでも頻繁に起こることは想定しがたい。

それに対して、重要影響事態法や国際平和支援法による「後方支援」の場合は、「使い勝手」のよい自衛隊の軍事行動として多用される危険が高いし、アメリカなどにとっては「大歓迎」であろう。また、外国軍の武器等防護のための武器使用も、日常的な警戒監視活動や演習などの際の突発的な軍事衝突に際して利用できる点で「重宝」である。しかし、そこから本格的な軍事行動すなわち集団的自衛権の行使へと展開していく危険が内包されている。改正国際平和協力法による自衛隊のPKO その他での活動の拡大は、その軍隊としての熟練の重要な機会となり、また国際的ステイタスの確保の場として位置付けられているのであろう。しかし、それは、他国の「正式の軍隊」並みに危険な戦闘に関わることを意味するのである。 |
 |
2. 戦争法の意味

 こうした戦争法は、どのような意味を、とりわけ憲法9条との関係で、持つのであろうか。実は、そこには憲法9条が歩んできた歴史が投影されていて、「二つの意味」が含まれている。このことをしっかりつかまえることが重要である。 こうした戦争法は、どのような意味を、とりわけ憲法9条との関係で、持つのであろうか。実は、そこには憲法9条が歩んできた歴史が投影されていて、「二つの意味」が含まれている。このことをしっかりつかまえることが重要である。

 第一の意味は、戦争法が、戦後一貫して憲法9条を歪めてきた日米安保体制を、従来までの到達の上に立って、さらに前進させたという点である。戦争法の制定に先立つ2015年4月、日米両政府は、「日米防衛協力の指針」(ガイドライン)を取り交わした。このガイドラインは、1978年、1997年に続く三つ目のものである。これら3つのガイドラインは、それらが策定された時代状況、そこで日米安保体制が当面した課題や、国内外の政治的対抗などに規定されて、その内容に差があるものの、「アメリカからの日本に対する軍事分担拡大の要求書」という点では、共通の性格を持っている。3つのガイドラインによって一貫して追求されてきたものは、安保条約5条が想定する「日本に対する武力攻撃」以外の海外における事態で、何についてどの程度日米間で軍事的に協力するかということであった。その意味において、ガイドラインは、日米安保条約の法的枠組みの限界さえも踏み越えて、軍事同盟としての日米安保体制を強化する手段としての意義を担わされている。 第一の意味は、戦争法が、戦後一貫して憲法9条を歪めてきた日米安保体制を、従来までの到達の上に立って、さらに前進させたという点である。戦争法の制定に先立つ2015年4月、日米両政府は、「日米防衛協力の指針」(ガイドライン)を取り交わした。このガイドラインは、1978年、1997年に続く三つ目のものである。これら3つのガイドラインは、それらが策定された時代状況、そこで日米安保体制が当面した課題や、国内外の政治的対抗などに規定されて、その内容に差があるものの、「アメリカからの日本に対する軍事分担拡大の要求書」という点では、共通の性格を持っている。3つのガイドラインによって一貫して追求されてきたものは、安保条約5条が想定する「日本に対する武力攻撃」以外の海外における事態で、何についてどの程度日米間で軍事的に協力するかということであった。その意味において、ガイドラインは、日米安保条約の法的枠組みの限界さえも踏み越えて、軍事同盟としての日米安保体制を強化する手段としての意義を担わされている。

 このガイドラインという「めがね」を通して戦争法を見ると、その本質的性格がよくわかる。ガイドラインは、冒頭でその目的として、「切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共同の対応」、「日米同盟のグローバルな性質」を強調している。この間安倍首相などがよく口にする「切れ目のない安全保障法制」や「積極的平和主義」なる言葉は、ガイドラインがいう「グローバルな日米同盟」という文脈においてこそ、その意味が鮮明になる。なお、ここで留意しておかねばならないことは、日米安保体制が、その出発点から今日まで、いかに日本国憲法を、その9条の平和主義はもちろんのこと、立憲主義、民主主義を蝕んできたか、蝕んでいるかということである。 このガイドラインという「めがね」を通して戦争法を見ると、その本質的性格がよくわかる。ガイドラインは、冒頭でその目的として、「切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共同の対応」、「日米同盟のグローバルな性質」を強調している。この間安倍首相などがよく口にする「切れ目のない安全保障法制」や「積極的平和主義」なる言葉は、ガイドラインがいう「グローバルな日米同盟」という文脈においてこそ、その意味が鮮明になる。なお、ここで留意しておかねばならないことは、日米安保体制が、その出発点から今日まで、いかに日本国憲法を、その9条の平和主義はもちろんのこと、立憲主義、民主主義を蝕んできたか、蝕んでいるかということである。

 日米安保体制の軸をなす日米安保条約は、日本国憲法を踏みにじりながら誕生した。憲法9条は、「戦力の不保持」を定めた9条2項を素直に読めば、「非武装平和主義」を定めている。本誌の昨年の5月号(632号)掲載の畑田重夫氏の論稿「改憲への道を暴走する安倍政権」が、「原点論」として、憲法9条2項の意義を強調しているのは、重要な指摘である。その憲法9条2項が、いつどのように歪められたかというと、それは1951年の(旧)安保条約の締結による米軍駐留の容認と、1950年の警察予備隊の設置から始まり1954年の自衛隊の創設にいたる再軍備によってである。 日米安保体制の軸をなす日米安保条約は、日本国憲法を踏みにじりながら誕生した。憲法9条は、「戦力の不保持」を定めた9条2項を素直に読めば、「非武装平和主義」を定めている。本誌の昨年の5月号(632号)掲載の畑田重夫氏の論稿「改憲への道を暴走する安倍政権」が、「原点論」として、憲法9条2項の意義を強調しているのは、重要な指摘である。その憲法9条2項が、いつどのように歪められたかというと、それは1951年の(旧)安保条約の締結による米軍駐留の容認と、1950年の警察予備隊の設置から始まり1954年の自衛隊の創設にいたる再軍備によってである。

 講和後の日本の平和保障のあり方をめぐっては、占領下の日本国内では、知識人やマスコミによって「全面講和・中立・外国基地反対・非武装」という憲法9条に則った構想が語られていた。ところが朝鮮戦争の勃発により、また日本にとって深刻なこととしては、ソ連のスターリンによる日本共産党への「軍事方針」の押しつけなどもあり、「朝鮮半島での動乱は対岸の火事ではない」、「共産主義の脅威が日本にも迫っている」、「(ソ連・中国を含む)全面講和や中立は非現実的」、「自由主義国家の一員となる(=米軍に基地を提供する)」という吉田内閣の主張が勢いを増して、アメリカを中心とする片面講和、安保条約の締結へと至ることになる。 講和後の日本の平和保障のあり方をめぐっては、占領下の日本国内では、知識人やマスコミによって「全面講和・中立・外国基地反対・非武装」という憲法9条に則った構想が語られていた。ところが朝鮮戦争の勃発により、また日本にとって深刻なこととしては、ソ連のスターリンによる日本共産党への「軍事方針」の押しつけなどもあり、「朝鮮半島での動乱は対岸の火事ではない」、「共産主義の脅威が日本にも迫っている」、「(ソ連・中国を含む)全面講和や中立は非現実的」、「自由主義国家の一員となる(=米軍に基地を提供する)」という吉田内閣の主張が勢いを増して、アメリカを中心とする片面講和、安保条約の締結へと至ることになる。

この時、サンフランシスコ講和条約の直後に吉田首相がアメリカと締結した安保条約の内容は、事前にはいっさい国民や国会にも知らされなかった。そしてまた、安保条約が、日本にとってきわめて不利な一方的な基地提供条約(片務的条約)となるに当たっては、昭和天皇サイドの外交が絶大な効果を発揮したという研究もある(豊下楢彦『昭和天皇の戦後日本 <憲法・安保体制> にいたる道』岩波書店・2015年)。

 かくして、政府は、講和後に安保条約によって駐留する米軍について、「憲法9条2項にいう『戦力』とは、我が国の戦力のことであって、外国軍隊はこれに当たらない」という「木で鼻をくくる」かのような理屈で、これを正当化していくことになる。また、「一切の戦力を放棄した結果、自衛のためであっても武力の行使はできない」という憲法制定時の解釈を曲げて、「自衛のための必要最小限度の実力は合憲」という解釈を、自衛隊創設後の1954年に打ち出していくことになる。 かくして、政府は、講和後に安保条約によって駐留する米軍について、「憲法9条2項にいう『戦力』とは、我が国の戦力のことであって、外国軍隊はこれに当たらない」という「木で鼻をくくる」かのような理屈で、これを正当化していくことになる。また、「一切の戦力を放棄した結果、自衛のためであっても武力の行使はできない」という憲法制定時の解釈を曲げて、「自衛のための必要最小限度の実力は合憲」という解釈を、自衛隊創設後の1954年に打ち出していくことになる。

このように9条2項にほんらい違反する安保条約による米軍駐留の容認や自衛隊の創設による再軍備は、平和主義、民主主義、立憲主義のいずれをも破壊する形で行われていくのである。現在の日米安保体制の下におかれた憲法9条のあり方の「原型」が、このようにして作られたことを、しっかりと認識しておこう。

 日米安保体制の民主主義、立憲主義に反する性格は、2015年のガイドライン合意においても貫かれている。ガイドラインは、その政治的重要性にもかかわらず、安保条約や地位協定のような法的な性格を有する条約ではなく、単なる「政治的文書」という形式で取り交わされている。 日米安保体制の民主主義、立憲主義に反する性格は、2015年のガイドライン合意においても貫かれている。ガイドラインは、その政治的重要性にもかかわらず、安保条約や地位協定のような法的な性格を有する条約ではなく、単なる「政治的文書」という形式で取り交わされている。

2015年のガイドラインには、「基本的な前提及び考え方」として「安保条約およびその関連取極めに基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは変更されない」、「日本の行動及び活動は、専守防衛、非核三原則等の日本の基本的な方針に従って行われる」、「ガイドラインはいずれの政府にも立法上、予算上、行政上又はその他の措置をとることを義務付けるものではなく、また、ガイドラインはいずれの政府にも法的権利または義務を生じさせるものではない」などの言葉が並んでいる。

しかし、こうした言葉にもかかわらず、このガイドラインが日米両政府によって合意されたというのは紛れもない政治的現実である。しかし、ガイドラインは、「法的文書ではなく政治的文書」という性格ゆえに、国会での追及を難なく免れてしまっている。その内容に照らして考えると、きわめて重大なことといわねばならない。ガイドラインが、国会や国民による議論をすり抜けている状況は、民主主義の観点からゆゆしき問題である。

 このように日米安保体制がもつ平和主義、民主主義、立憲主義に対する本質的な敵対的、侵害的性格、すなわち日本国憲法の体制と根本的に相いれないことをしっかりと見すえ、戦争法の問題性もその発露であることをとらえることが肝心である。 このように日米安保体制がもつ平和主義、民主主義、立憲主義に対する本質的な敵対的、侵害的性格、すなわち日本国憲法の体制と根本的に相いれないことをしっかりと見すえ、戦争法の問題性もその発露であることをとらえることが肝心である。

 戦争法のもう一つの意味は、これまで日米安保体制と自衛隊の存在によってゆがめられてきたとはいえ、それでも国民の運動によって、9条の明文改憲を許さずにきたこと、そのことによって「専守防衛」、「集団的自衛権行使は違憲」、「他国の武力行使と一体化はしない」などの、欺瞞と矛盾を含んだものではあれ、憲法9条の「縛り」を前提した理屈を政府に唱えさせてきたこと、それを今回の戦争法は踏み越えたということである。 戦争法のもう一つの意味は、これまで日米安保体制と自衛隊の存在によってゆがめられてきたとはいえ、それでも国民の運動によって、9条の明文改憲を許さずにきたこと、そのことによって「専守防衛」、「集団的自衛権行使は違憲」、「他国の武力行使と一体化はしない」などの、欺瞞と矛盾を含んだものではあれ、憲法9条の「縛り」を前提した理屈を政府に唱えさせてきたこと、それを今回の戦争法は踏み越えたということである。

 前述のように、政府は、もともと憲法制定時に9条2項は「一切の戦力」の不保持を定めたとしていたのに、1954年には既成事実となった自衛隊の存在を、憲法解釈をねじ曲げて正当化をはかる挙に出た。今回の戦争法につながる2014年の閣議決定もそうだが、政府は、重大な憲法違反をする時は、必ずと言ってよいほど恣意的な「理屈」を組み立てる。新たな憲法解釈をひねり出して、それを何とか正当化しようとする。これは、いつの世でも、またどのような政策でも、権力が繰り出す政治の「常套(じょうとう)手段」といえる。私たちは、主権者として、この厳然たる事実をしっかりと認識しておく必要がある。 前述のように、政府は、もともと憲法制定時に9条2項は「一切の戦力」の不保持を定めたとしていたのに、1954年には既成事実となった自衛隊の存在を、憲法解釈をねじ曲げて正当化をはかる挙に出た。今回の戦争法につながる2014年の閣議決定もそうだが、政府は、重大な憲法違反をする時は、必ずと言ってよいほど恣意的な「理屈」を組み立てる。新たな憲法解釈をひねり出して、それを何とか正当化しようとする。これは、いつの世でも、またどのような政策でも、権力が繰り出す政治の「常套(じょうとう)手段」といえる。私たちは、主権者として、この厳然たる事実をしっかりと認識しておく必要がある。

 しかし、このとき同時に、政府は、自らに「制約」を課した。それが「集団的自衛権は違憲」という論理である。これがなければ、国民の強い反対世論を押し切って自衛隊を正当化することは困難であった。政治は、権力が「真空地帯」で行うものではない。国民主権という大原則のもと、権力は、自らに反対する勢力も含む国民に対してその「正当性」を示さねばならない。その結果、権力の「立ち位置」は、平和と民主主義、人権の保障を求めて権力と対峙する国民の世論の力との対抗関係のなかで定まってくるのである。それによってしか、権力は自らの正当性を主張しえないというのが、国民主権、民主主義のもとでの政治の通常の姿である。 しかし、このとき同時に、政府は、自らに「制約」を課した。それが「集団的自衛権は違憲」という論理である。これがなければ、国民の強い反対世論を押し切って自衛隊を正当化することは困難であった。政治は、権力が「真空地帯」で行うものではない。国民主権という大原則のもと、権力は、自らに反対する勢力も含む国民に対してその「正当性」を示さねばならない。その結果、権力の「立ち位置」は、平和と民主主義、人権の保障を求めて権力と対峙する国民の世論の力との対抗関係のなかで定まってくるのである。それによってしか、権力は自らの正当性を主張しえないというのが、国民主権、民主主義のもとでの政治の通常の姿である。

だからこそ、私たち国民が声をあげ、政治に関わることが重要になる。実際に、この間の戦争法反対ー廃止運動で示されている市民のパワーは、従来の政府が、曲がりなりにも維持してきた「憲法9条の縛り」を自覚した政策を、一内閣の閣議決定で、しかもきわめてずさんな理屈でくつがえして恥じるところのない安倍内閣の姿勢に、「いまこそ主権者としての声をあげるとき」と決意した人々の声が唱和したところに生まれている。その一方で、安倍首相は、昨年成立させた戦争法の施行(2016年3月)もなされる前から、「憲法9条2項の改正」や「緊急事態条項の導入」などの明文改憲論を公言している。

これは、戦争法を無理やり成立させたものの、そのためには「集団的自衛権の行使は限定的」、「他国の武力行使との一体化はしない」、「武装組織ISを空爆する有志連合への後方支援は政策判断として行わない」などの「弁解」に終始して、南スーダンPKOなどでのその発動も、「政治的影響」を考慮して参議院選挙後にせざるを得ないという状況に対する彼なりの危機感の現れと見ることができる。すなわち「明文改憲をあきらめていない」という姿勢を示すことで、かろうじて「戦争法廃止」の世論に対抗できると考えているのであろう。

しかし、これは、戦争法の危険性をより一層際立たせることに他ならない。「緊急事態条項の導入」論の口実としてきた「自然災害への対応」も、この間の九州での地震への対応の状況という事実によって、何ら根拠のないものが明らかになりつつある。自然災害への対処であれば、災害対策基本法をはじめとして、現にある法律が周到な対処規定を用意している。「緊急事態条項」のような白紙委任的な規定は必要でない。この規定は、軍事行動の自由を強く求める軍事的有事においてこそ意義と威力を発揮する。「お試し改憲」どころか9条改憲とワンセットの企みである。 |
 |
むすびにかえて - 戦争法廃止の展望

 今まさに、戦争法の廃止を通じて、国民が自らの手で、憲法の本来の姿を取り戻して、この国の政治を憲法に根付かせる絶好の機会が私たちの目の前にある。戦争法がもつ立憲主義・民主主義・平和主義の侵害的性格は、日米ガイドラインに通底するものであり、そうした性格は、日米安保体制にその根源をさかのぼることができる。戦争法の廃止によって立憲主義・民主主義・平和主義を取り戻すことは、日米安保体制を問い直すこと、それによって日本国憲法が志向する国家・社会を実現することに通ずる課題でもある。戦争法廃止運動の中で、このことについて旺盛に論じ、対話を重ねよう。 今まさに、戦争法の廃止を通じて、国民が自らの手で、憲法の本来の姿を取り戻して、この国の政治を憲法に根付かせる絶好の機会が私たちの目の前にある。戦争法がもつ立憲主義・民主主義・平和主義の侵害的性格は、日米ガイドラインに通底するものであり、そうした性格は、日米安保体制にその根源をさかのぼることができる。戦争法の廃止によって立憲主義・民主主義・平和主義を取り戻すことは、日米安保体制を問い直すこと、それによって日本国憲法が志向する国家・社会を実現することに通ずる課題でもある。戦争法廃止運動の中で、このことについて旺盛に論じ、対話を重ねよう。 |
 |
<参考文献>

 「戦後70年、憲法の危機と日米同盟」『学習の友別冊 戦後70年と憲法・民主主義・安保』(学習の友社・2015年8月) 「戦後70年、憲法の危機と日米同盟」『学習の友別冊 戦後70年と憲法・民主主義・安保』(学習の友社・2015年8月)
 「戦争法案の息の根を止めようー『安保環境』論・『抑止力』論にどう向き合うか」月刊憲法運動444号(2015年9月) 「戦争法案の息の根を止めようー『安保環境』論・『抑止力』論にどう向き合うか」月刊憲法運動444号(2015年9月)
 「戦争法廃止・憲法9条を守り平和な日本をー立憲主義・民主主義・平和主義をつなぐものー」労働総研クォータリー2016年冬号(2015年12月) 「戦争法廃止・憲法9条を守り平和な日本をー立憲主義・民主主義・平和主義をつなぐものー」労働総研クォータリー2016年冬号(2015年12月)
 「平和主義、立憲主義、民主主義を侵害する日米ガイドライン」日本の科学者579号(2016年4月) 「平和主義、立憲主義、民主主義を侵害する日米ガイドライン」日本の科学者579号(2016年4月)
 「戦争法を廃止して立憲主義・民主主義・平和主義を取り戻すことの意義」前衛934号(2016年5月) 「戦争法を廃止して立憲主義・民主主義・平和主義を取り戻すことの意義」前衛934号(2016年5月) |
(おざわ・りゅういち) |