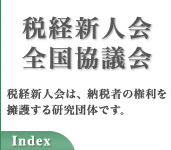本事例の土地の評価、建物の評価、取り毀し費用の控除を、相続税の評価にあたってどのような方法でもって実現することが出来るか。 本事例の土地の評価、建物の評価、取り毀し費用の控除を、相続税の評価にあたってどのような方法でもって実現することが出来るか。

事例

 市街地に存する宅地の上に使用不能の鉄筋コンクリート四階建ての築50年の元診療所が存する。 市街地に存する宅地の上に使用不能の鉄筋コンクリート四階建ての築50年の元診療所が存する。
 宅地は、500m²、路線価4,000万円 宅地は、500m²、路線価4,000万円
 建物は、市の固定資産評価1,200万円 建物は、市の固定資産評価1,200万円
 建物の取り毀し費用は、概算1,000万円 建物の取り毀し費用は、概算1,000万円

 相続税評価にあたり、この宅地、建物の評価、及び建物の取り毀し費用の債務控除を如何にするかについて,評価通達に見当たらなかったので不動産鑑定士の鑑定評価によった。鑑定の要点は次の観点を基本に評価している。 相続税評価にあたり、この宅地、建物の評価、及び建物の取り毀し費用の債務控除を如何にするかについて,評価通達に見当たらなかったので不動産鑑定士の鑑定評価によった。鑑定の要点は次の観点を基本に評価している。

 市街地に存する物件につき、土地の再有効活用を想定して評価する。 市街地に存する物件につき、土地の再有効活用を想定して評価する。
 建物の価値は、ゼロとする。 建物の価値は、ゼロとする。
 土地の更地評価額から、建物の取り壊し費用相当額を差し引いて算出する。 土地の更地評価額から、建物の取り壊し費用相当額を差し引いて算出する。
 税務調査において、税務署の見解が次のとおり示された。 税務調査において、税務署の見解が次のとおり示された。
 評価は通達通りにすべきである。 評価は通達通りにすべきである。
 即ち、土地は路線価で、建物は市の評価で、建物の取り毀し費用は認めない。 即ち、土地は路線価で、建物は市の評価で、建物の取り毀し費用は認めない。
 その結果は、税務署の指摘通りに修正申告をした。 その結果は、税務署の指摘通りに修正申告をした。

検討資料

 相続税法第22条 ...相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。 相続税法第22条 ...相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

評価基本通達
1.(2)時価の意義
 財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額(加筆 客観的要素が考慮され、主観的要素は排除される)をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。 財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額(加筆 客観的要素が考慮され、主観的要素は排除される)をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。

(3)財産の評価
 財産の評価にあたっては、その財産の価額に影響を及ぼすべき全ての事情を考慮する。 財産の評価にあたっては、その財産の価額に影響を及ぼすべき全ての事情を考慮する。

6.この通達の定めにより難い場合の評価
 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

「解説」
 評価基本通達に定める評価方法を画一的に適用した場合には、適正な時価評価が求められず、その評価額が不適切なものとなり、著しく課税の公平を欠く場合も生じることが考えられる。このため、本項においては、そのような場合には個々の財産の態様に応じた適正な時価評価が行えるよう措置している。 評価基本通達に定める評価方法を画一的に適用した場合には、適正な時価評価が求められず、その評価額が不適切なものとなり、著しく課税の公平を欠く場合も生じることが考えられる。このため、本項においては、そのような場合には個々の財産の態様に応じた適正な時価評価が行えるよう措置している。
11. < 宅地の評価は >、原則として、市街地的形態を形成する地域にある宅地は、路線価方式によって行う。

(私見)
 宅地は、更地であるとした場合の価額を算出するのであるから、地上の物件を考慮する余地はないと言える。 宅地は、更地であるとした場合の価額を算出するのであるから、地上の物件を考慮する余地はないと言える。
 但し、通達には見当たらないが、資産税の本には、「利用状況などに応じた評価額の修正」 但し、通達には見当たらないが、資産税の本には、「利用状況などに応じた評価額の修正」
(10)利用価値の著しく低下している宅地として、例示がされている。(後記)
< 家屋の評価 >
 89.家屋の評価は、その家屋の固定資産評価額に別表1に定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。 89.家屋の評価は、その家屋の固定資産評価額に別表1に定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

(私見)
 実態は、廃屋などもあり個々にその価値は異なり、固定資産評価額と乖離している場合が散見される。 実態は、廃屋などもあり個々にその価値は異なり、固定資産評価額と乖離している場合が散見される。
 しかし、通達では、これらよくある実務上の評価方法が全く見当たらない。 しかし、通達では、これらよくある実務上の評価方法が全く見当たらない。
 固定資産評価は、実取引価額ではなく、理論上の価額であり、しかも幾ら古くなっても一定額以上の価額を維持している。 固定資産評価は、実取引価額ではなく、理論上の価額であり、しかも幾ら古くなっても一定額以上の価額を維持している。
 そこに、相続税評価方法が、固定資産評価額によっているところに大きなギャップが起こっていると言える。 そこに、相続税評価方法が、固定資産評価額によっているところに大きなギャップが起こっていると言える。

< 債務控除(建物の取り毀し費用)>
 相法13 相法13  ...被相続人の債務で相続開始の際、現に存するものを債務控除する。 ...被相続人の債務で相続開始の際、現に存するものを債務控除する。
 相法14 相法14  控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。 控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
 相基通14-1(確実な債務) 相基通14-1(確実な債務)

 債務が確実なものであるかどうかは、必ずしも書面の証拠があることを要しない。 債務が確実なものであるかどうかは、必ずしも書面の証拠があることを要しない。
 なお、債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを控除する。 なお、債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを控除する。

解説
 確実と認められる債務とは、債務の存在及び債権者による請求その他により債務者につきその債務の履行が義務づけられている債務と解される。が、この確実であるかどうかの判定をどのように行うかについての一般的な取扱を定めたのが、14-1の通達である。 確実と認められる債務とは、債務の存在及び債権者による請求その他により債務者につきその債務の履行が義務づけられている債務と解される。が、この確実であるかどうかの判定をどのように行うかについての一般的な取扱を定めたのが、14-1の通達である。

(私見)
 取り毀し費用は、相続開始時点において未だ発生していないので、控除できない、と言うことになる。 取り毀し費用は、相続開始時点において未だ発生していないので、控除できない、と言うことになる。

< 土壌汚染地の評価 >
 汚染が無いものとした土地の価額から次のものを控除する。 汚染が無いものとした土地の価額から次のものを控除する。
 浄化・改善費用に相当する金額 浄化・改善費用に相当する金額
 使用収益制限よる減価に相当する金額 使用収益制限よる減価に相当する金額
 心理的要因による減価に相当する金額 心理的要因による減価に相当する金額
 利用価値の著しく低下している宅地 利用価値の著しく低下している宅地
 普通住宅地にある宅地で、道路より高い位置にある宅地,地盤に著しい凸凹がある宅地等、利用価値が低下していると認められる部分の面積に応じて10%控除する。 普通住宅地にある宅地で、道路より高い位置にある宅地,地盤に著しい凸凹がある宅地等、利用価値が低下していると認められる部分の面積に応じて10%控除する。

< 土地の鑑定評価に関する先例 >
 請求人は、路線価には相続開始日までの地価下落が反映されておらず、実際の取引においても路線価では売却できないこと等から鑑定評価により評価すべきと主張するが、1月1日から相続開始日までの間に20%以上の下落あったとは認められないから路線価で評価すべきである。(H16.12. 3裁決、裁決事例集No.68 p170) 請求人は、路線価には相続開始日までの地価下落が反映されておらず、実際の取引においても路線価では売却できないこと等から鑑定評価により評価すべきと主張するが、1月1日から相続開始日までの間に20%以上の下落あったとは認められないから路線価で評価すべきである。(H16.12. 3裁決、裁決事例集No.68 p170)

 不動産鑑定は、一般的には客観的な根拠を有するものとして扱われるべきであり、その結果が通達評価額を下回るときはこれが時価にあたるが、採用した評価方法に高い合理性が必要である。として納税者の請求を認容した。(名古屋地裁平成16年8月30日判決、平15(行ウ)10号)(確定) 不動産鑑定は、一般的には客観的な根拠を有するものとして扱われるべきであり、その結果が通達評価額を下回るときはこれが時価にあたるが、採用した評価方法に高い合理性が必要である。として納税者の請求を認容した。(名古屋地裁平成16年8月30日判決、平15(行ウ)10号)(確定)

 家屋の評価に関する先例 家屋の評価に関する先例
 固定資産税評価額は、時価とはいえないという主張に対する審判所の判断(H18.12. 4裁決、裁決事例集No.不詳) 固定資産税評価額は、時価とはいえないという主張に対する審判所の判断(H18.12. 4裁決、裁決事例集No.不詳) |