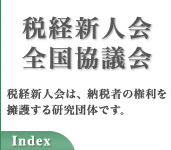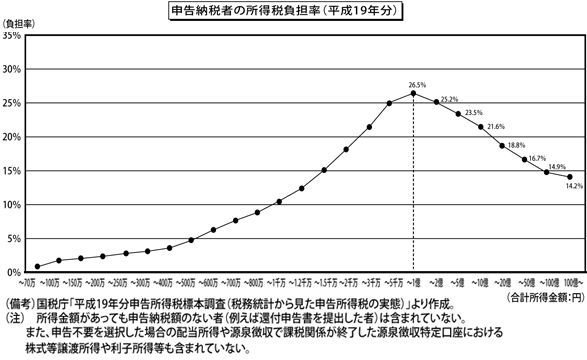| 1)4つの視点 |
| イ |
企業の国際競争力を強化するために法人税率の引き下げをしなければ、経済の空洞化はますます進行する。 |
| ロ |
大企業と中小企業は、生産から流通まで一体として機能しているので、国内での雇用の維持、需給のバランス、継続的成長を実現するためには、大企業と中小企業を区別せず一体的な改革を実現しなければならない。 |
| ハ |
財政の健全化、社会保障制度の維持のため、安定的財源を確保するために、消費税率の引き上げを含む税制の抜本的改革を早期に実現することが不可欠である。 |
| ニ |
少子高齢化、資源や環境問題、グローバル化などに対応して、ゼロベースから社会改革をすすめるという広義のイノベーション(これは経団連が主張する科学技術だけでなく、社会政策についての技術革新を意味させようとしているものです。)に取り組まなければならない。 |
 |
| 2)基本的経済政策の3つの柱 |
| イ |
国際競争力の維持と強化  ここでも法人税率の引き下げ、研究開発促進税制の拡充、政府の研究開発投資の更なる推進を求めています。 ここでも法人税率の引き下げ、研究開発促進税制の拡充、政府の研究開発投資の更なる推進を求めています。 |
| ロ |
規制緩和の推進、道州制、社会保障・税の共通番号制の導入などによる電子行政の推進、物流の効率化のためのインフラの整備、金融市場の規制緩和策等による高齢者の保有する1400兆円に及ぶ金融資産を市場に呼び込むことによる有効活用などが必要である。 |
| ハ |
柔軟性をもった労働市場を構築するため、労働者のライフスタイルに適応した働き方ができる多様な就労形態を準備する  つまり、労働法制の分野では派遣法の改正によって規制を強めることは適当ではない。 つまり、労働法制の分野では派遣法の改正によって規制を強めることは適当ではない。

 以上のような視点と経済政策における柱を前提にして、第3章ではこれらの視点や要求を実現するための各分野にわたる財界の要求が具体的に、ある分野では細部にわたって、あるいはある分野については極めて大雑把に羅列されています。 以上のような視点と経済政策における柱を前提にして、第3章ではこれらの視点や要求を実現するための各分野にわたる財界の要求が具体的に、ある分野では細部にわたって、あるいはある分野については極めて大雑把に羅列されています。 |
 |
3)成長の実現に向けた6つの戦略とは、その標題に沿って紹介すると次のとおりです。
イ 環境エネルギー大国戦略
ロ 健康大国戦略
ハ アジア経済戦略
ニ 観光立国・地域活性化戦略
ホ 科学・技術立国戦略
ヘ 雇用・人材戦略

 これらの戦略を推進するためには、それを阻害する各種の障害、つまり、国民、労働者、農家等を保護するための各種の規制や制約は取り払わなければならないということになります。そのうえで、いよいよその戦略を実行する経済的な裏付けとなる税制、財政、社会保障制度の一体的改革の内容が示されることになります。それが第4章に述べられている「成長戦略にかかわる税・財政・社会保障の一体改革」です。 これらの戦略を推進するためには、それを阻害する各種の障害、つまり、国民、労働者、農家等を保護するための各種の規制や制約は取り払わなければならないということになります。そのうえで、いよいよその戦略を実行する経済的な裏付けとなる税制、財政、社会保障制度の一体的改革の内容が示されることになります。それが第4章に述べられている「成長戦略にかかわる税・財政・社会保障の一体改革」です。 |
 この負担率は、国税庁「平成19年分申告所得標本調査(税務統計から見た申告所得税の実態)」から作成されたものですが、この数値の中には「申告不要を選択した場合の配当所得や源泉徴収で課税関係が終了した源泉徴収特定口座における株式譲渡所得や利子所得等」が含まれていません(同資料の〔注〕参照)。株の取引きや配当で所得を得ている人は、大資産家が圧倒的に多いので、もし、それらの実態が統計上明らかにされ、このグラフに加算されて比較することができれば、高額所得者の負担率は、限りなく10%に近づいていくことになります。 この負担率は、国税庁「平成19年分申告所得標本調査(税務統計から見た申告所得税の実態)」から作成されたものですが、この数値の中には「申告不要を選択した場合の配当所得や源泉徴収で課税関係が終了した源泉徴収特定口座における株式譲渡所得や利子所得等」が含まれていません(同資料の〔注〕参照)。株の取引きや配当で所得を得ている人は、大資産家が圧倒的に多いので、もし、それらの実態が統計上明らかにされ、このグラフに加算されて比較することができれば、高額所得者の負担率は、限りなく10%に近づいていくことになります。

 このような、財界の要求によって歪められた個人所得課税の制度に、所得再分配機能や「基幹税」としての税収の確保を求めても、それは土台から無理な話ということになります。かつて昭和58年分までは最高税率が所得税で75%、個人住民税で18%、合計93%という時代があり、それもかなり長く続いたのです。その後数次の最高税率の引き下げが行われて現在に至っているわけですが、このような高度の累進税率によって、総合課税の分野では所得再配分機能を割によく果たしていたわけです。 このような、財界の要求によって歪められた個人所得課税の制度に、所得再分配機能や「基幹税」としての税収の確保を求めても、それは土台から無理な話ということになります。かつて昭和58年分までは最高税率が所得税で75%、個人住民税で18%、合計93%という時代があり、それもかなり長く続いたのです。その後数次の最高税率の引き下げが行われて現在に至っているわけですが、このような高度の累進税率によって、総合課税の分野では所得再配分機能を割によく果たしていたわけです。

 もちろん、その間にも、シャウプ税制における個人所得課税の根幹である総合累進課税を破壊する制度改悪は何度も行われました。その最たるものが土地譲渡所得に対する分離軽課制度です。この制度は、高度成長政策を支えるための農地の宅地化、市街地周辺土地の開発の推進による大手ゼネコン中心の公共事業の推進の土台を築くなどの「成果」をもたらしました。その最終的な結果が異状な土地バブル現象を発生させ、その崩壊が日本経済の長期的不況の引き金になったことは広く知られているところです。 もちろん、その間にも、シャウプ税制における個人所得課税の根幹である総合累進課税を破壊する制度改悪は何度も行われました。その最たるものが土地譲渡所得に対する分離軽課制度です。この制度は、高度成長政策を支えるための農地の宅地化、市街地周辺土地の開発の推進による大手ゼネコン中心の公共事業の推進の土台を築くなどの「成果」をもたらしました。その最終的な結果が異状な土地バブル現象を発生させ、その崩壊が日本経済の長期的不況の引き金になったことは広く知られているところです。

 利子所得については、シャウプ税制の導入以来実は一度も完全に総合課税化されたことがありません。最高税率が93%の時代において、35%の源泉分離課税が実施され、多額の金融資産を持つ大資産家は、最高税率93%の4割未満の35%で利子所得に対する課税は完了したわけです。その後、グリーンカード制度などの議論はありましたが、最終的には現行の20%(国税15%、住民税5%)になっています。それも、強制分離課税ですから低所得のため所得が課税最低限以下で納税義務のない人でも、申告によって取り戻すことはできません。 利子所得については、シャウプ税制の導入以来実は一度も完全に総合課税化されたことがありません。最高税率が93%の時代において、35%の源泉分離課税が実施され、多額の金融資産を持つ大資産家は、最高税率93%の4割未満の35%で利子所得に対する課税は完了したわけです。その後、グリーンカード制度などの議論はありましたが、最終的には現行の20%(国税15%、住民税5%)になっています。それも、強制分離課税ですから低所得のため所得が課税最低限以下で納税義務のない人でも、申告によって取り戻すことはできません。

 配当所得についても事情はほぼ同じような変遷をたどってきました。源泉分離課税は、高額の配当についても利子と同様35%の時代が続きました。その後減税に次ぐ減税が行われ上場株式の配当については、特定口座に基づく10%(国税7%、地方税3%)の分離課税になっています。特定口座制度の導入に伴って株式の売買による所得も配当と同様10%の分離課税で課税関係を完結させるか、株式の売買損失が出た場合は配当と損益通算ができることとするほか、控除しきれない損失額が出た場合は翌年以降に繰越控除することを選択できるといういわば「何でもあり」の優遇措置がとられるようになりました。それが現行法では平成23年まで続くことになっていますが、経団連は「二元的所得税制」として、金融取引における所得を、他の所得と完全に分離して所得税を二本建てにして金融取引(利子、配当、有価証券の売買によるもの)を総合課税の所得と完全に切り放すことを求めています。 配当所得についても事情はほぼ同じような変遷をたどってきました。源泉分離課税は、高額の配当についても利子と同様35%の時代が続きました。その後減税に次ぐ減税が行われ上場株式の配当については、特定口座に基づく10%(国税7%、地方税3%)の分離課税になっています。特定口座制度の導入に伴って株式の売買による所得も配当と同様10%の分離課税で課税関係を完結させるか、株式の売買損失が出た場合は配当と損益通算ができることとするほか、控除しきれない損失額が出た場合は翌年以降に繰越控除することを選択できるといういわば「何でもあり」の優遇措置がとられるようになりました。それが現行法では平成23年まで続くことになっていますが、経団連は「二元的所得税制」として、金融取引における所得を、他の所得と完全に分離して所得税を二本建てにして金融取引(利子、配当、有価証券の売買によるもの)を総合課税の所得と完全に切り放すことを求めています。

 総論としての税制改革の方向としては、「消費税率を一刻も早く引き上げ、所得税の基幹税としての機能を回復し(証券優遇税制などの大資産家・高額所得者優遇税制を維持するかぎり、所得税が基幹税としての機能を回復することは到底できません 関本)、法人税への過度な依存を改め、社会保障給付をはじめとする中長期的な歳出の増大に耐えられる税体系の構築を一体的に講ずること」を求めています。結局、消費税増税と法人税減税が一貫した要求であることの再確認です。各論を検討してみましょう。 総論としての税制改革の方向としては、「消費税率を一刻も早く引き上げ、所得税の基幹税としての機能を回復し(証券優遇税制などの大資産家・高額所得者優遇税制を維持するかぎり、所得税が基幹税としての機能を回復することは到底できません 関本)、法人税への過度な依存を改め、社会保障給付をはじめとする中長期的な歳出の増大に耐えられる税体系の構築を一体的に講ずること」を求めています。結局、消費税増税と法人税減税が一貫した要求であることの再確認です。各論を検討してみましょう。 |
 |
(1)消費税
 西欧諸国の15%〜 25%に比べてわが国の5%はあまりにも低すぎるので早急に引き上げることが求められています。消費税は特定の者に負担が集中せず、経済活動への影響が中立的であるという「優れた特徴をもっている」ので、「社会保障費用の増加分には消費税率の引き上げによって対応するとの原則(消費税の社会保障目的税化)」を確立するよう求めています。 西欧諸国の15%〜 25%に比べてわが国の5%はあまりにも低すぎるので早急に引き上げることが求められています。消費税は特定の者に負担が集中せず、経済活動への影響が中立的であるという「優れた特徴をもっている」ので、「社会保障費用の増加分には消費税率の引き上げによって対応するとの原則(消費税の社会保障目的税化)」を確立するよう求めています。

 具体的な引き上げ幅は、たとえば毎年2%ずつ引き上げ、少なくとも2020年代半ばまでに10%台後半(16%ないし19%ということです。)ないしはそれ以上へ引き上げるというものです。 具体的な引き上げ幅は、たとえば毎年2%ずつ引き上げ、少なくとも2020年代半ばまでに10%台後半(16%ないし19%ということです。)ないしはそれ以上へ引き上げるというものです。

 消費税負担率の逆進性対策としては、複数税率(ゼロ税率または軽減税率)はとらず、低中所得者には生活必需品に係る消費税率引き上げ相当額を定額で還付する制度を導入するという制度の創設を提言しています。 消費税負担率の逆進性対策としては、複数税率(ゼロ税率または軽減税率)はとらず、低中所得者には生活必需品に係る消費税率引き上げ相当額を定額で還付する制度を導入するという制度の創設を提言しています。

 消費税増税による景気への影響については97年の3%から5%への引き上げによる不況の深刻化をもたらした経験は無視して、むしろ物価上昇を見越した「消費の前倒し効果」が期待できるという楽観論を主張しています。このような主張に根拠がないことは歴史の経験から明らかです。2%ずつの引き上げとなれば、毎年5兆円規模の増税で、消費購買力を奪うことになるわけですから、消費不況をさらに深刻化させ、日本経済の将来を破滅させてしまうことは明らかです。 消費税増税による景気への影響については97年の3%から5%への引き上げによる不況の深刻化をもたらした経験は無視して、むしろ物価上昇を見越した「消費の前倒し効果」が期待できるという楽観論を主張しています。このような主張に根拠がないことは歴史の経験から明らかです。2%ずつの引き上げとなれば、毎年5兆円規模の増税で、消費購買力を奪うことになるわけですから、消費不況をさらに深刻化させ、日本経済の将来を破滅させてしまうことは明らかです。

 さらに輸出戻し税が大企業優遇税制ではないかという批判に対しては、消費税が国内消費に課税されるものであるから国際的にも広く認められた仕組みであり、批判は当たらないと反論していますが、実態は自動車産業に顕著に見られるように、毎年のように下請単価の引き下げを要求し、事実上大企業自らは負担せず、負担していない消費税を輸出に際して年額で2兆円ないし3兆円(国税庁資料によると平成19年度で3兆4400億円)の還付を受け続けているという実態については全く無視しようとしています。下請中小企業は、単価の切り下げによって赤字経営を強いられていながら、売り上げがあるかぎり消費税の負担は避けられず、倒産や廃業を余儀なくされているという現状は全く顧みようとはしません。 さらに輸出戻し税が大企業優遇税制ではないかという批判に対しては、消費税が国内消費に課税されるものであるから国際的にも広く認められた仕組みであり、批判は当たらないと反論していますが、実態は自動車産業に顕著に見られるように、毎年のように下請単価の引き下げを要求し、事実上大企業自らは負担せず、負担していない消費税を輸出に際して年額で2兆円ないし3兆円(国税庁資料によると平成19年度で3兆4400億円)の還付を受け続けているという実態については全く無視しようとしています。下請中小企業は、単価の切り下げによって赤字経営を強いられていながら、売り上げがあるかぎり消費税の負担は避けられず、倒産や廃業を余儀なくされているという現状は全く顧みようとはしません。 |
 |
(2)所得税の再分配機能の回復
 個人所得税における所得再分配機能の喪失は先にみたように高額所得者や大資産家優遇の各種分離課税や軽減税率の適用などによるものですが、経団連の主張にはそのことは全く触れられてはいません。ではどうやって所得再分配機能を回復するのかといえば、「社会保障・税共通の番号制度の導入による公平な所得捕捉」を実施し、各種所得控除を見直し「課税最低限以下の所得者には給付を行うことのできる『給付付き税額控除』制度を導入する」という、民主党のマニフェストにすり寄るような所得税改革を提言しています。 個人所得税における所得再分配機能の喪失は先にみたように高額所得者や大資産家優遇の各種分離課税や軽減税率の適用などによるものですが、経団連の主張にはそのことは全く触れられてはいません。ではどうやって所得再分配機能を回復するのかといえば、「社会保障・税共通の番号制度の導入による公平な所得捕捉」を実施し、各種所得控除を見直し「課税最低限以下の所得者には給付を行うことのできる『給付付き税額控除』制度を導入する」という、民主党のマニフェストにすり寄るような所得税改革を提言しています。

 そこで、見直しの対象となるのは、まず労働者の賃金に対する課税の強化です。つまり給与所得控除を圧縮することが考えられています。また、配偶者控除も見直しのやり玉にあげられています。 そこで、見直しの対象となるのは、まず労働者の賃金に対する課税の強化です。つまり給与所得控除を圧縮することが考えられています。また、配偶者控除も見直しのやり玉にあげられています。

 公的年金控除も例外ではありません。社会保険料の負担時に所得控除されているのだから、給付時にさらに公的年金控除をするのは二重控除になり、高齢者を過度に優遇するものだというのがその理由です。さらに、年金を受けながら給与を得ている高齢者は、給与所得控除と公的年金控除の重複になるので、これも見直せというのですから、その主張は悪名高い「後期高齢者医療保険制度」も顔負けするような手前勝手の主張といわれても反論できないでしょう。 公的年金控除も例外ではありません。社会保険料の負担時に所得控除されているのだから、給付時にさらに公的年金控除をするのは二重控除になり、高齢者を過度に優遇するものだというのがその理由です。さらに、年金を受けながら給与を得ている高齢者は、給与所得控除と公的年金控除の重複になるので、これも見直せというのですから、その主張は悪名高い「後期高齢者医療保険制度」も顔負けするような手前勝手の主張といわれても反論できないでしょう。

 さらに、累進課税による最高税率の引き上げは、経済活力に対して悪影響を及ぼすおそれがあるだけでなく、それによる増収効果も乏しいので、最高税率の引き上げは好ましくない(表現としては「見直しは・・・慎重に検討」となっていますが)という態度をとっています。 さらに、累進課税による最高税率の引き上げは、経済活力に対して悪影響を及ぼすおそれがあるだけでなく、それによる増収効果も乏しいので、最高税率の引き上げは好ましくない(表現としては「見直しは・・・慎重に検討」となっていますが)という態度をとっています。

 また、高額所得者、大資産家を極端に優遇している金融所得課税(主として証券優遇税制)については、これを総合課税とするどころか、「金融所得について損益通算の範囲拡大および繰越損失の容認など、金融所得課税のさらなる一元化を検討すべきである」と主張しています。これは現在の証券優遇税制だけでは不十分であるから、最終的には「二元的所得税」制ともいうべき金融所得課税の完全分離を射程にいれた主張とみるべきだと思います。 また、高額所得者、大資産家を極端に優遇している金融所得課税(主として証券優遇税制)については、これを総合課税とするどころか、「金融所得について損益通算の範囲拡大および繰越損失の容認など、金融所得課税のさらなる一元化を検討すべきである」と主張しています。これは現在の証券優遇税制だけでは不十分であるから、最終的には「二元的所得税」制ともいうべき金融所得課税の完全分離を射程にいれた主張とみるべきだと思います。

 このように検討してくると、個人所得課税における再分配機能の回復ではなくそのかぎりない破壊、不公平税制のかぎりない拡大を求めているのが経団連提言であるといわなければなりません。 このように検討してくると、個人所得課税における再分配機能の回復ではなくそのかぎりない破壊、不公平税制のかぎりない拡大を求めているのが経団連提言であるといわなければなりません。 |
 |
(3)法人税制
 法人税制については、欧米諸国や途上国の法人負担率を表面的な数字を持ち出して、わが国の法人実効税率は高すぎるとして、実効税率を10%程度引き下げることを主張しています。わが国においては、大企業に対する各種特別措置によって課税ベースが著しく侵食されていること、そして社会保障費の企業負担が先進国に比較して著しく低いこと、これらのことを総合的に勘案した実質税負担率がかなり低くなっていることなどが故意に無視されています。さらに提言が掲げている国際比較をみてもフランスやスウェーデンよりも低く、ドイツとほぼ同水準であり、イギリス、アメリカなど新自由主義の主導国だけが日本よりも低水準であることがわかります。 法人税制については、欧米諸国や途上国の法人負担率を表面的な数字を持ち出して、わが国の法人実効税率は高すぎるとして、実効税率を10%程度引き下げることを主張しています。わが国においては、大企業に対する各種特別措置によって課税ベースが著しく侵食されていること、そして社会保障費の企業負担が先進国に比較して著しく低いこと、これらのことを総合的に勘案した実質税負担率がかなり低くなっていることなどが故意に無視されています。さらに提言が掲げている国際比較をみてもフランスやスウェーデンよりも低く、ドイツとほぼ同水準であり、イギリス、アメリカなど新自由主義の主導国だけが日本よりも低水準であることがわかります。

 さらに重要なことは、労働者派遣法などによって企業の労働者に対する搾取が、わが国においては他の先進国に比べて突出して厳しいものとなり、それが独占的大企業の収益力を高めていることです。したがって、グローバル化したわが国の独占的大企業の内部蓄積は、世界的な不況の中で驚くべき速さで増加しています。利潤の絶対的大きさは、多少の税負担の差など問題にしない程になり類まれな競争力を発揮している点こそ重要だと思います。 さらに重要なことは、労働者派遣法などによって企業の労働者に対する搾取が、わが国においては他の先進国に比べて突出して厳しいものとなり、それが独占的大企業の収益力を高めていることです。したがって、グローバル化したわが国の独占的大企業の内部蓄積は、世界的な不況の中で驚くべき速さで増加しています。利潤の絶対的大きさは、多少の税負担の差など問題にしない程になり類まれな競争力を発揮している点こそ重要だと思います。

 このような実態を見るかぎり、法人の実効税率の引き下げの要求には何ら現実的にも理論的にも根拠がないといえます。 このような実態を見るかぎり、法人の実効税率の引き下げの要求には何ら現実的にも理論的にも根拠がないといえます。 |
 |
(4)社会保障・税共通番号制
 経団連の納税者番号制度についての提言は次のようなものです。 経団連の納税者番号制度についての提言は次のようなものです。

 住民票コードあるいは社会保障番号などを活用して納税者の正確な所得を把握することが可能となるので、経団連の主張する株式譲渡所得、配当所得、利子所得など金融所得課税の一元化を推進するとともに、これまで税制、社会保障負担、給付で別々に行われてきた政策を一本化させ、「給付付き税額控除制度を導入する」というものです。 住民票コードあるいは社会保障番号などを活用して納税者の正確な所得を把握することが可能となるので、経団連の主張する株式譲渡所得、配当所得、利子所得など金融所得課税の一元化を推進するとともに、これまで税制、社会保障負担、給付で別々に行われてきた政策を一本化させ、「給付付き税額控除制度を導入する」というものです。

 共通納税者番号制度は、国民の一元的管理のための道具にすぎず、それによって総合累進課税の制度を強化して個人所得課税の所得再分配機能を再構築しようという発想は全くありません。また、それにより侵害されかねない個人情報の保護措置についても全く触れられていません。 共通納税者番号制度は、国民の一元的管理のための道具にすぎず、それによって総合累進課税の制度を強化して個人所得課税の所得再分配機能を再構築しようという発想は全くありません。また、それにより侵害されかねない個人情報の保護措置についても全く触れられていません。

 むしろ、消費税率の引き上げによる大増税に備えて、いわゆる納税環境の整備、税務行政の効率化に資することに主なねらいがあるものと思われます。 むしろ、消費税率の引き上げによる大増税に備えて、いわゆる納税環境の整備、税務行政の効率化に資することに主なねらいがあるものと思われます。

 総合累進課税の徹底や強化によって所得税の再分配機能を強化するためには、現在の法定調書の制度を活用することで十分対応できる筈ですから、いまさら改めて共通番号制度の導入は必要ありません。 総合累進課税の徹底や強化によって所得税の再分配機能を強化するためには、現在の法定調書の制度を活用することで十分対応できる筈ですから、いまさら改めて共通番号制度の導入は必要ありません。 |