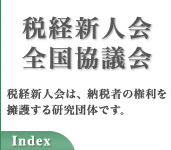1 序

 憲法は、税に関して30条で「法律なくして納税なしの原則」を84条で「法律なくして課税なしの原則」をうたっている。これらの原則は「租税法律主義」といわれる。 憲法は、税に関して30条で「法律なくして納税なしの原則」を84条で「法律なくして課税なしの原則」をうたっている。これらの原則は「租税法律主義」といわれる。

 日本国憲法の下においては、国民が主権者であり、政府が行う国政は国民によって信託されているにすぎない(憲法前文)。ここで保障されている基本的人権は、行政権および司法権はもちろん、立法権に対しても保障されたものである。 日本国憲法の下においては、国民が主権者であり、政府が行う国政は国民によって信託されているにすぎない(憲法前文)。ここで保障されている基本的人権は、行政権および司法権はもちろん、立法権に対しても保障されたものである。

 ところが現実には基本的人権を侵害する税務行政が横たわっている。一般的にいって、憲法の条文やそれについての解説を知っていても、それを日常生活の上で実現しなければ、憲法的感覚が身についたとはいえない。 ところが現実には基本的人権を侵害する税務行政が横たわっている。一般的にいって、憲法の条文やそれについての解説を知っていても、それを日常生活の上で実現しなければ、憲法的感覚が身についたとはいえない。

 そこで、納税者の力を強くするためには、生活の中で憲法的感覚をやしない、憲法を道具として、生活要求を実現するような実践行動が、納税者の日常生活のなかで不断に行わなければならない。 そこで、納税者の力を強くするためには、生活の中で憲法的感覚をやしない、憲法を道具として、生活要求を実現するような実践行動が、納税者の日常生活のなかで不断に行わなければならない。

 税務調査における適正手続の問題など、納税者の人権意識が広範に日常生活の中で育てられることが、租税法律主義を生かす真の土台となる。この点で、1951年に結成された企業の生活と権利をまもる立場から、税制・税務行政の民主的改革を求める運動をつうじ、また、たえざる弾圧と闘いながら、納税者の権利をまもり、ひろめてきた。この運動が日本における納税者の権利意識の成長の基礎となっている。 税務調査における適正手続の問題など、納税者の人権意識が広範に日常生活の中で育てられることが、租税法律主義を生かす真の土台となる。この点で、1951年に結成された企業の生活と権利をまもる立場から、税制・税務行政の民主的改革を求める運動をつうじ、また、たえざる弾圧と闘いながら、納税者の権利をまもり、ひろめてきた。この運動が日本における納税者の権利意識の成長の基礎となっている。

 このような運動は、明治以来の天皇制支配のもとで極端に納税者を抑圧してきた課税権力(課税庁)にとっては好ましいわけはない。1963(昭和38)年5月には、木村秀弘国税庁長官が、全国国税局長会議において「3年以内に民商を徹底的にやっつける」と発言し、民商弾圧を始めた。一連の弾圧事件の一つが荒川民商「広田事件」である。 このような運動は、明治以来の天皇制支配のもとで極端に納税者を抑圧してきた課税権力(課税庁)にとっては好ましいわけはない。1963(昭和38)年5月には、木村秀弘国税庁長官が、全国国税局長会議において「3年以内に民商を徹底的にやっつける」と発言し、民商弾圧を始めた。一連の弾圧事件の一つが荒川民商「広田事件」である。 |
 |
2 荒川民商「広田事件」

(1)事件の概要

 1966(昭和41)年9月、個人事業者広田権次郎氏(プレス加工業)の工場に荒川税務署所得税第2課友井係長と同課森事務官が税務調査に訪れた。対応した広田権次郎氏(以下「広田氏」という)と広田氏の長男広田真一氏(以下「真一氏」という)は調査理由の開示を求めた。税務署員が開示を拒否したので、言い争いになった。 1966(昭和41)年9月、個人事業者広田権次郎氏(プレス加工業)の工場に荒川税務署所得税第2課友井係長と同課森事務官が税務調査に訪れた。対応した広田権次郎氏(以下「広田氏」という)と広田氏の長男広田真一氏(以下「真一氏」という)は調査理由の開示を求めた。税務署員が開示を拒否したので、言い争いになった。

署員の1人は帰り際に、長男所持の大学ノートが手に当たったと主張。否定する長男を無視して帰署した署員は、上司の指示で「示指(人差し指)全治3日間の打撲傷」の診断書を嘱託医に書かせ、警察に提出した。数日後の早朝、広田氏の工場に約90人もの警察官が向かい、広田氏と真一氏を逮捕した。鶴見祐策弁護士の尽力で、両名は3日後に釈放された。税務署の告発を受けた検察は、所得税法(当時、現在は国税通則法に規定)に規定する検査等拒否犯(質問不答弁と検査拒否)で広田氏を起訴した。

 東京地裁における弁護人は、上田誠吉、鶴見祐策、西嶋勝彦、佐藤義行、池田輝孝他のそうそうたるメンバー、加えて税経新人会の吉田敏幸、田中健介の両税理士が特別弁護人として尽力した。法廷は毎回、民商会員らが埋め尽くし、当時の河野貞三郎全商連会長や進藤甚四郎事務局長も証言台に立った。 東京地裁における弁護人は、上田誠吉、鶴見祐策、西嶋勝彦、佐藤義行、池田輝孝他のそうそうたるメンバー、加えて税経新人会の吉田敏幸、田中健介の両税理士が特別弁護人として尽力した。法廷は毎回、民商会員らが埋め尽くし、当時の河野貞三郎全商連会長や進藤甚四郎事務局長も証言台に立った。

 東京地方裁判所刑事9部の戸田弘裁判官(裁判長)、米沢敏雄裁判官、堀籠幸男裁判官は以下の無罪判決を下した。 東京地方裁判所刑事9部の戸田弘裁判官(裁判長)、米沢敏雄裁判官、堀籠幸男裁判官は以下の無罪判決を下した。

(2)東京地裁判決

 以下は東京地裁判決(1969〈昭和44〉年6月25日)の概要である。 以下は東京地裁判決(1969〈昭和44〉年6月25日)の概要である。
【主文】
 被告人は無罪。 被告人は無罪。
【理由】

1. 公訴事実
 判決文は次のように述べている。 判決文は次のように述べている。
 本件公訴事実は、「被告人は、東京都荒川区町屋4丁目24番17号に工場を持ってプレス加工業を営み、所得税の納税義務がある者であるが、昭和41年9月12日午前10時50分ごろから同11時35分ごろまでの間、右工場入口で、東京国税局荒川税務署所得税第2課所得税第2係長大蔵事務官友井淳一、同第2係勤務大蔵事務官森啓の両名が、被告人に対する昭和40年分所得税確定申告調査のため、同人および被告人の長男廣田真一に対し質問するとともに、右事業に関する帳簿書類を検査しようとしてその呈示等を求めた際、右真一と共謀のうえ、右両名に対し、『何度話しても同じだ。もう帰ってくれ』、『生活の保障がない限り答えられない』、『調査はさせない』などと怒鳴りながら両手で右森の腰部を押すなどし、もって右友井らの質問に対して答弁せず、かつ検査を拒んだものである」というのであり、検察官は、右の事実が刑法60条、所得税法242条8号に該当する旨主張している。 本件公訴事実は、「被告人は、東京都荒川区町屋4丁目24番17号に工場を持ってプレス加工業を営み、所得税の納税義務がある者であるが、昭和41年9月12日午前10時50分ごろから同11時35分ごろまでの間、右工場入口で、東京国税局荒川税務署所得税第2課所得税第2係長大蔵事務官友井淳一、同第2係勤務大蔵事務官森啓の両名が、被告人に対する昭和40年分所得税確定申告調査のため、同人および被告人の長男廣田真一に対し質問するとともに、右事業に関する帳簿書類を検査しようとしてその呈示等を求めた際、右真一と共謀のうえ、右両名に対し、『何度話しても同じだ。もう帰ってくれ』、『生活の保障がない限り答えられない』、『調査はさせない』などと怒鳴りながら両手で右森の腰部を押すなどし、もって右友井らの質問に対して答弁せず、かつ検査を拒んだものである」というのであり、検察官は、右の事実が刑法60条、所得税法242条8号に該当する旨主張している。

2. 公訴事実に関して認められる事実(概要)

 調査官は1966年8月18日と23日の二回、さらに同年9月7日、被告人方に行ったが、いずれも押し問答になり、調査の目的を遂げられなかった。そこで、同調査官は、再び同月12日午前10時50分ごろ、被告人方に行き、被告人とその長男真一に会った。そして、友井係長は、昭和40年分の所得税につき所得税法234条の質問検査権にもとづいて必要があって調査するということおよび調査に応じないと罰則にふれるということを告げ、帳簿書類を見せてほしい、得意先、仕入先の住所氏名をいってほしい、工場内を見せてほしいという趣旨を述べた。 調査官は1966年8月18日と23日の二回、さらに同年9月7日、被告人方に行ったが、いずれも押し問答になり、調査の目的を遂げられなかった。そこで、同調査官は、再び同月12日午前10時50分ごろ、被告人方に行き、被告人とその長男真一に会った。そして、友井係長は、昭和40年分の所得税につき所得税法234条の質問検査権にもとづいて必要があって調査するということおよび調査に応じないと罰則にふれるということを告げ、帳簿書類を見せてほしい、得意先、仕入先の住所氏名をいってほしい、工場内を見せてほしいという趣旨を述べた。

被告人は、見せられない、いえないと述べ、その前後に、真一が「何度話してもおなじだから、もう帰ってくれ」というようなことをいい、また被告人が「生活の保障がないかぎり答えられない」という意味のことをいつたりもした。そして、押問答のすえ、最後には、友井が真一から右手を打たれたと感じて、「暴力で調査を拒否するのか」といつたやりとりがあり、同時に、被告人が森のからだを押すというようなことがあつた。しかし、いずれにせよ、被告人ないし真一の側に、刑法上特に暴行として問題とするに価するほどの行動があつたわけではない。

3. 所得税法242条8号の罪の成立要件(概要)

 所得税法242条8号(筆者注。当時の条文。以下所得税法は当時の条文。現在は国税通則法に規定)の罪の構成要件は、同法234条1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避することである。そして、同法234条1項は、「国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる」と定め、同項一号は、「納税義務がある者、納税義務があると認められる者」その他を掲げている。 所得税法242条8号(筆者注。当時の条文。以下所得税法は当時の条文。現在は国税通則法に規定)の罪の構成要件は、同法234条1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避することである。そして、同法234条1項は、「国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる」と定め、同項一号は、「納税義務がある者、納税義務があると認められる者」その他を掲げている。

 ここに、「納税義務がある者」、「納税義務があると認められる者」というのは、たしかに明確な表現ではないが、質問検査権に関する立法の沿革および所得税が申告納税方式によるものであることを考慮すると、「納税義務がある者」というのは、確定申告書を提出することにより所得税の納付義務が確定している者(その税額の全部または一部をすでに納付しているかどうかを問わない)を意味し、「納税義務があると認められる者」とは、確定申告書を提出していないけれども、客観的、実質的に納税義務が成立しているものと合理的に推認され、確定申告書を提出すべきであつたと認められる者を意味するものと解すべきである。 ここに、「納税義務がある者」、「納税義務があると認められる者」というのは、たしかに明確な表現ではないが、質問検査権に関する立法の沿革および所得税が申告納税方式によるものであることを考慮すると、「納税義務がある者」というのは、確定申告書を提出することにより所得税の納付義務が確定している者(その税額の全部または一部をすでに納付しているかどうかを問わない)を意味し、「納税義務があると認められる者」とは、確定申告書を提出していないけれども、客観的、実質的に納税義務が成立しているものと合理的に推認され、確定申告書を提出すべきであつたと認められる者を意味するものと解すべきである。

従って、本件の場合、被告人は「納税義務がある者」にあたることになる。なお、本件では被告人の納付すべき所得税に関する調査のための質問検査が問題となっているのであるから、真一は「納税義務がある者」でも、「納税義務があると認められる者」でもありえないことが明らかである。ところで、所得税法234条1項にいう当該職員(この概念を特に不明確ということはできない)は、所得税に関する調査のため、合理的な必要性があるかぎり、同項各号に掲げる者に質問してその任意の回答をえ、またはこれらの者の任意の承諾をえてその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することが許されるのであり、その許される場合は、きわめて広範囲にわたるものといつてよい。

 しかし、右のような質問ないし検査(させること)の求めに対する単なる不答弁ないし拒否が同法242条8号の罪を構成するためには、さらに厳重な要件を必要とするものといわなければならない。なぜなら、当該職員が必要と認めて質問し、検査を求めるかぎり、不答弁や検査の拒否がどのような場合にも1年以下の懲役または20万円以下の罰金にあたることになるものとすれば、事柄が所得税に関する調査というほとんどすべての国民が対象になるような広範囲の一般的事項であり、しかも直接公共の安全などにかかわる問題でもないだけに、刑罰法規としてあまりにも不合理なものとなり、憲法31条(筆者注、適正手続)のもとに有効に存立しえないことになるからである。 しかし、右のような質問ないし検査(させること)の求めに対する単なる不答弁ないし拒否が同法242条8号の罪を構成するためには、さらに厳重な要件を必要とするものといわなければならない。なぜなら、当該職員が必要と認めて質問し、検査を求めるかぎり、不答弁や検査の拒否がどのような場合にも1年以下の懲役または20万円以下の罰金にあたることになるものとすれば、事柄が所得税に関する調査というほとんどすべての国民が対象になるような広範囲の一般的事項であり、しかも直接公共の安全などにかかわる問題でもないだけに、刑罰法規としてあまりにも不合理なものとなり、憲法31条(筆者注、適正手続)のもとに有効に存立しえないことになるからである。

 すなわち、所得税法242条8号の罪は、その質問等について合理的な必要性が認められるばかりでなく、その不答弁等を処罰の対象とすることが不合理といえないような特段の事情が認められる場合にのみ、成立するものというべきである(なお、このように解するかぎり、所得税法242条8号について、憲法35条〈筆者注、住居の不可侵〉あるいは38条1項〈筆者注、不利益な供述を強要されない〉違反の問題も生じる余地がないものといわなければならない)。 すなわち、所得税法242条8号の罪は、その質問等について合理的な必要性が認められるばかりでなく、その不答弁等を処罰の対象とすることが不合理といえないような特段の事情が認められる場合にのみ、成立するものというべきである(なお、このように解するかぎり、所得税法242条8号について、憲法35条〈筆者注、住居の不可侵〉あるいは38条1項〈筆者注、不利益な供述を強要されない〉違反の問題も生じる余地がないものといわなければならない)。

 本件のように、「納税義務がある者」すなわち確定申告書の提出者に対する場合には、必要があるかぎり、確定申告書ないしその添付書類の記載自体(その根拠に立ち入るのではなく)に対する説明を求めるため、刑罰を背景として質問することは、もとより許される。また、青色申告の場合には、所得計算上および納税手続上の特典があるかわりに、所定の帳簿書類の備付が義務づけられているのであるから、これらの帳簿書類の検査を拒否すれば、処罰を受けることもやむをえない。 本件のように、「納税義務がある者」すなわち確定申告書の提出者に対する場合には、必要があるかぎり、確定申告書ないしその添付書類の記載自体(その根拠に立ち入るのではなく)に対する説明を求めるため、刑罰を背景として質問することは、もとより許される。また、青色申告の場合には、所得計算上および納税手続上の特典があるかわりに、所定の帳簿書類の備付が義務づけられているのであるから、これらの帳簿書類の検査を拒否すれば、処罰を受けることもやむをえない。

 しかし、被告人のように、一般のいわゆる白色申告者である場合には、単に、帳簿書類を見せてほしい、得意先、仕入先の住所氏名をいってほしい、工場内を見せてほしいといわれただけで、これに応じなかつたからといつて、ただちに不答弁ないし検査拒否として処罰の対象になるものと考えることはできない。荒川税務署が過少申告の疑いを持ったことが合理的であるとしても、それだけの事由で、刑罰の威嚇のもとに、包括的に帳簿書類一切を見せることを要求し、包括的に得意先、仕入先全部の住所氏名を告げることを要求し、さらには工場内を見せることを求めることが合理的に許されるものとは、到底いいがたい。 しかし、被告人のように、一般のいわゆる白色申告者である場合には、単に、帳簿書類を見せてほしい、得意先、仕入先の住所氏名をいってほしい、工場内を見せてほしいといわれただけで、これに応じなかつたからといつて、ただちに不答弁ないし検査拒否として処罰の対象になるものと考えることはできない。荒川税務署が過少申告の疑いを持ったことが合理的であるとしても、それだけの事由で、刑罰の威嚇のもとに、包括的に帳簿書類一切を見せることを要求し、包括的に得意先、仕入先全部の住所氏名を告げることを要求し、さらには工場内を見せることを求めることが合理的に許されるものとは、到底いいがたい。

 本件の場合、友井係長も森事務官も、当初森事務官が一人で行ったとき以来、ただ調査の必要があるからというだけで、その理由は、被告人らから再三聞かれても、一切意識的にこれを説明していないのである。 本件の場合、友井係長も森事務官も、当初森事務官が一人で行ったとき以来、ただ調査の必要があるからというだけで、その理由は、被告人らから再三聞かれても、一切意識的にこれを説明していないのである。

 そもそも、税務当局としては、国税犯則の嫌疑があって真に強力な手段を必要とするならば、国税犯則取締法にもとづき、裁判官の許可状を得て、臨検、捜索または差押ができるのであり、司法官憲の令状発付手続の介在による抑制の作用しないところで、係官の任意の選択により、安易に一般的、包括的に、答弁や検査承諾の間接強制が許されるものと解することは、なんとしても不当である。要するに、本件の場合には、被告人の前記のような行為は、これを処罰の対象とすることが不合理といえないような特段の事情が認められないため、所得税法242条8号の罪を構成するに足りないものといわなければならない。 そもそも、税務当局としては、国税犯則の嫌疑があって真に強力な手段を必要とするならば、国税犯則取締法にもとづき、裁判官の許可状を得て、臨検、捜索または差押ができるのであり、司法官憲の令状発付手続の介在による抑制の作用しないところで、係官の任意の選択により、安易に一般的、包括的に、答弁や検査承諾の間接強制が許されるものと解することは、なんとしても不当である。要するに、本件の場合には、被告人の前記のような行為は、これを処罰の対象とすることが不合理といえないような特段の事情が認められないため、所得税法242条8号の罪を構成するに足りないものといわなければならない。

4. 結論

 以上のとおり、本件公訴事実については、結局犯罪の証明がないことに帰するから、刑訴336条により無罪の言渡をする。 以上のとおり、本件公訴事実については、結局犯罪の証明がないことに帰するから、刑訴336条により無罪の言渡をする。

 なお、本件の捜査および訴追が民主商工会運動に対する弾圧、特に荒川民主商工会の組織破壊をねらいとするものであり、本件公訴提起は、公訴権乱用の場合にあたり、不適法であるという弁護人らの主張については、公判にあらわれた種々の資料によれば、本件の実質的な背景になっているのは、税務当局による民主商工会運動に対する規制措置ないし反撃であるとみることもあながち根拠がないものとはいいがたいし、また、被告人方を実際に見れば(当裁判所の検証調書参照)、なぜにこのような零細きわまる業者について本件のような訴追をしなければならなかったのかという疑問を抱くものが多いであろうが、特に、質問検査拒否罪の成立要件が従前明確でなかつたことを考慮すると、本件の公訴提起が極限的に不当であるとは到底いえないから、公訴棄却の裁判をなすべき場合にはあたらない。 なお、本件の捜査および訴追が民主商工会運動に対する弾圧、特に荒川民主商工会の組織破壊をねらいとするものであり、本件公訴提起は、公訴権乱用の場合にあたり、不適法であるという弁護人らの主張については、公判にあらわれた種々の資料によれば、本件の実質的な背景になっているのは、税務当局による民主商工会運動に対する規制措置ないし反撃であるとみることもあながち根拠がないものとはいいがたいし、また、被告人方を実際に見れば(当裁判所の検証調書参照)、なぜにこのような零細きわまる業者について本件のような訴追をしなければならなかったのかという疑問を抱くものが多いであろうが、特に、質問検査拒否罪の成立要件が従前明確でなかつたことを考慮すると、本件の公訴提起が極限的に不当であるとは到底いえないから、公訴棄却の裁判をなすべき場合にはあたらない。 |
 |
3 荒川民商事件の勝訴と運動の前進

 東京地裁は、以上のように広田氏を無罪とした。その後、控訴審の東京高裁では罰金3万円の有罪、上告審の最高裁で棄却された。しかし、東京地裁の勝訴判決は民主的な税務行政を求める運動を勇気付け、次に一部例示する有力な道具を納税者運動に与えた。 東京地裁は、以上のように広田氏を無罪とした。その後、控訴審の東京高裁では罰金3万円の有罪、上告審の最高裁で棄却された。しかし、東京地裁の勝訴判決は民主的な税務行政を求める運動を勇気付け、次に一部例示する有力な道具を納税者運動に与えた。

(1)72国会で採択の請願

 72国会(1973〈昭和48〉年12月1日〜1974年6月3日)において衆議院大蔵委員会は1974年6月3日、次の「中小業者に対する税制改正等に関する請願」を採択した。 72国会(1973〈昭和48〉年12月1日〜1974年6月3日)において衆議院大蔵委員会は1974年6月3日、次の「中小業者に対する税制改正等に関する請願」を採択した。

1. 税制改革について
(1)現行の事業主報酬を改め、青色・白色を問わず店主・家族専従者の自家労賃を認め、完全給与制とすること。
(2)大資本に対する特権的な租税特別措置を無くし、法人税を累進制とし、小法人の税率を大幅に引き下げること、等。

2. 税務行政の改善については、税務調査に当たり事前に納税者に通知するとともに、調査の理由を開示すること。

(2)税務運営方針

 国税庁は1976(昭和51)年4月1日、納税者を尊重する内容を含んだ税務運営方針を発表した。この方針は、「納税者が自ら進んで適正な申告と納税を行うような態勢にすること」として、近づきやすい税務署にするとして次のように述べている。 国税庁は1976(昭和51)年4月1日、納税者を尊重する内容を含んだ税務運営方針を発表した。この方針は、「納税者が自ら進んで適正な申告と納税を行うような態勢にすること」として、近づきやすい税務署にするとして次のように述べている。

 納税者が自ら進んで適正な申告と納税を行うようになるには、納税者が租税の意義を理解し、その義務を自覚するとともに、税法を理解し、正しい計算のために記帳方法などの知識を持つことが必要である。このため、広報、説明会、税務相談などを通じて、納税についての理解を深め、税法等の知識を普及するとともに、記帳慣習を育成することに努める。特に課税標準の調査に当っては、事実関係を的確には握し、納税者の誤りを是正しなければならないことはもちろんであるが、単にそれにとどまらないで、それを契機に、納税者が税務知識を深め、更に進んで納税意識をも高めるように努めなければならない。 納税者が自ら進んで適正な申告と納税を行うようになるには、納税者が租税の意義を理解し、その義務を自覚するとともに、税法を理解し、正しい計算のために記帳方法などの知識を持つことが必要である。このため、広報、説明会、税務相談などを通じて、納税についての理解を深め、税法等の知識を普及するとともに、記帳慣習を育成することに努める。特に課税標準の調査に当っては、事実関係を的確には握し、納税者の誤りを是正しなければならないことはもちろんであるが、単にそれにとどまらないで、それを契機に、納税者が税務知識を深め、更に進んで納税意識をも高めるように努めなければならない。

(3)行政手続法

 行政手続法は、1993年に成立し、1994年10月1日から施行された。同法1条(目的は、「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」とうたい、修正申告の勧奨、「お尋ね」、「呼び出し」等の行政指導について「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」とした(35条1項)。 行政手続法は、1993年に成立し、1994年10月1日から施行された。同法1条(目的は、「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」とうたい、修正申告の勧奨、「お尋ね」、「呼び出し」等の行政指導について「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」とした(35条1項)。 |
 |
4 調査の適正手続に係る課題

 広義の納税者の権利(課税における「応能負担原則」、税の使途は「福祉社会保障目的」、税務行政の「適正手続」等)は、未成熟な権利、いわば、「つかみとる運動を背景にした生成の途上にある権利」である。 広義の納税者の権利(課税における「応能負担原則」、税の使途は「福祉社会保障目的」、税務行政の「適正手続」等)は、未成熟な権利、いわば、「つかみとる運動を背景にした生成の途上にある権利」である。

 課税権力と納税者との対抗関係における力の貫徹、その利益の主張は、自己の支配領域を、相手方も承認する客観的規範において、定着する。このような客観的規範化によって、その力の貫徹、利益の主張は、単なる主張の域から分離し、権利的な性格を持つものとなる。これが完成された権利である。 課税権力と納税者との対抗関係における力の貫徹、その利益の主張は、自己の支配領域を、相手方も承認する客観的規範において、定着する。このような客観的規範化によって、その力の貫徹、利益の主張は、単なる主張の域から分離し、権利的な性格を持つものとなる。これが完成された権利である。

 社会的に成立する権利は、具体的な力くらべの中から、具体的な権利主張をとおして、しだいに、具体的支配から離れて独立した客観化の過程をたどりつつ、完成された形態に達する。けっして、無から有が生ずるように、権利でない状態から権利が突然に生ずるわけではない。 社会的に成立する権利は、具体的な力くらべの中から、具体的な権利主張をとおして、しだいに、具体的支配から離れて独立した客観化の過程をたどりつつ、完成された形態に達する。けっして、無から有が生ずるように、権利でない状態から権利が突然に生ずるわけではない。

法物神性(法律万能主義)にとりつかれた法実証主義的世界観(実定法に視野を限定する思考)においては、権利は法によってつくられ与えられるものであるかのごとく考えられている。だから、法が認める場合には、ある利益は、完全に権利としての存在が認められ、法が認めない場合には、それは、まったく権利的性を欠くとされる。権利を持つか持たないか、権利が完全にあるか、まったくないか、の二者択一の論理が貫かれる。しかし、権利の有無は二者選択ではなく、権力との対抗関係、力関係における問題である。

 納税者憲章確立運動についていうなら、今まで権利が存在しない状態において、憲章が与えられることによって、一躍して、突然に完全な憲章が求める権利が存在する状態に転化する、すなわち無権利納税者がたちまち権利者になるというたぐいのものでない。適正手続は、手続無視の権力にたいして適正手続をまもれという実践の課程において漸次的に憲章として成立し成長するものである。 納税者憲章確立運動についていうなら、今まで権利が存在しない状態において、憲章が与えられることによって、一躍して、突然に完全な憲章が求める権利が存在する状態に転化する、すなわち無権利納税者がたちまち権利者になるというたぐいのものでない。適正手続は、手続無視の権力にたいして適正手続をまもれという実践の課程において漸次的に憲章として成立し成長するものである。

 2017年度税制改定は、国税通則法(通則法)と国税犯則取締法(国犯法)を合体した。 2017年度税制改定は、国税通則法(通則法)と国税犯則取締法(国犯法)を合体した。

 国犯法の規定は通則法に新しく設けた11章に混入したが、国犯法22条にあった「扇動罪」については11章からはずし、通則法10章(罰則)126条に潜入させた。 国犯法の規定は通則法に新しく設けた11章に混入したが、国犯法22条にあった「扇動罪」については11章からはずし、通則法10章(罰則)126条に潜入させた。

 扇動罪は、納税義務者に申告不履行、虚偽申告、不徴収、不納付を扇動する(1項)、申告不履行、虚偽申告、不徴収、不納付を目的に暴行・脅迫を加えること(2項)を構成要件としている。扇動とは、他人に対して正しい判断を失わせて実行させ、または間違った判断を助長させる刺激を与えることである。刑法の教唆(61条)、幇助(62条)と異なりその意味は曖昧である。 扇動罪は、納税義務者に申告不履行、虚偽申告、不徴収、不納付を扇動する(1項)、申告不履行、虚偽申告、不徴収、不納付を目的に暴行・脅迫を加えること(2項)を構成要件としている。扇動とは、他人に対して正しい判断を失わせて実行させ、または間違った判断を助長させる刺激を与えることである。刑法の教唆(61条)、幇助(62条)と異なりその意味は曖昧である。

 喫茶店に「平和のために再軍備の徴税に反対しよう」という趣旨のビラを置いたことが扇動罪に問われた事件がある。この事件について、最高裁は、扇動行為があれば扇動罪は成立し、他人が犯罪を実行しなくても、ビラを置いただけで扇動罪になるとした(最高裁第一小法廷、昭和29年5月20日)。 喫茶店に「平和のために再軍備の徴税に反対しよう」という趣旨のビラを置いたことが扇動罪に問われた事件がある。この事件について、最高裁は、扇動行為があれば扇動罪は成立し、他人が犯罪を実行しなくても、ビラを置いただけで扇動罪になるとした(最高裁第一小法廷、昭和29年5月20日)。

 扇動罪は濫用されれば危険であるという論者がいる。この考えには弱点がある。この論理は、逆に言えば濫用されなければ悪くないという考えを承認するものである。濫用が悪いというのでは、一切の他の法律について同様なことがいえる。課税庁は濫用しない、反対者は濫用するという水掛け論に終る。納税者にとっては、「濫用されれば」という仮定ではなく、「濫用の必然性」の予見が必要である。必然性の一つは扇動罪の条文が、濫用を予定して制定されている点であり、他の一つは現行調査権の運用が将来の事態の予測を裏付ける事実を提供している点にある。 扇動罪は濫用されれば危険であるという論者がいる。この考えには弱点がある。この論理は、逆に言えば濫用されなければ悪くないという考えを承認するものである。濫用が悪いというのでは、一切の他の法律について同様なことがいえる。課税庁は濫用しない、反対者は濫用するという水掛け論に終る。納税者にとっては、「濫用されれば」という仮定ではなく、「濫用の必然性」の予見が必要である。必然性の一つは扇動罪の条文が、濫用を予定して制定されている点であり、他の一つは現行調査権の運用が将来の事態の予測を裏付ける事実を提供している点にある。

 法規の条文は、できるだけ、その意味が具体的にわかるように書くのが優れた立法的構成であり、濫用の危険がなくなる。通則法126条は、抽象的であり、その意味は、どうにでも解釈できるようになっている。わざとそうしたのか、立法技術的に稚拙なのか、のどちらかであるが、立法にあったって慎重に検討したというのであるから、おそらく後者ではなかろう。課税庁が本当に濫用を戒めるつもりがあるなら、意味がどのようにでもとれる法律を制定することはなかったのである。濫用されなければ危険なのではなく、条文そのものが危険を内包しているのである。 法規の条文は、できるだけ、その意味が具体的にわかるように書くのが優れた立法的構成であり、濫用の危険がなくなる。通則法126条は、抽象的であり、その意味は、どうにでも解釈できるようになっている。わざとそうしたのか、立法技術的に稚拙なのか、のどちらかであるが、立法にあったって慎重に検討したというのであるから、おそらく後者ではなかろう。課税庁が本当に濫用を戒めるつもりがあるなら、意味がどのようにでもとれる法律を制定することはなかったのである。濫用されなければ危険なのではなく、条文そのものが危険を内包しているのである。

 憲法13条は、国民の権利として、生命、自由とならんで「幸福追求に対する国民の権利」をうたっている。納税者の権利は外からやってくるものではなく、自分がつかみとるものである。非支配階級の人々は、あくまでも主体的に幸福を追求する精神をもち続けなければならない。憲法は「基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」(97条)と、この自由と権利は「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」(12条)としている。 憲法13条は、国民の権利として、生命、自由とならんで「幸福追求に対する国民の権利」をうたっている。納税者の権利は外からやってくるものではなく、自分がつかみとるものである。非支配階級の人々は、あくまでも主体的に幸福を追求する精神をもち続けなければならない。憲法は「基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」(97条)と、この自由と権利は「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」(12条)としている。

 法が課税権力を拘束するものだという民主主義的な法治主義の実現にいっそうの努力が求められる。 法が課税権力を拘束するものだという民主主義的な法治主義の実現にいっそうの努力が求められる。 |
(うらの・ひろあき) |