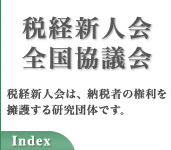| 1. |
 この憲章で、納税者とは、直接あるいは間接に税金またはこれに準ずる公的負担をしているすべての者を含みます。したがって、納税者という言葉は国民という言葉と同義語であると解さなければなりません。 この憲章で、納税者とは、直接あるいは間接に税金またはこれに準ずる公的負担をしているすべての者を含みます。したがって、納税者という言葉は国民という言葉と同義語であると解さなければなりません。
 |
| 2. |
 納税者は、すべて憲法25 条に保障された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障されています。したがって、最低生活費ならびに最低生活を維持するために必要な生存権的な財産に対して課税されることはありません。 納税者は、すべて憲法25 条に保障された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障されています。したがって、最低生活費ならびに最低生活を維持するために必要な生存権的な財産に対して課税されることはありません。
 この規定を実効あるものにするため、課税最低限は国税、地方税を問わず全国一律に大都市における生活保護基準を下まわらないよう設定されるとともに、財産課税においては最低生活を維持するために必要な土地建物等に対する課税が行われないように措置されなければなりません。 この規定を実効あるものにするため、課税最低限は国税、地方税を問わず全国一律に大都市における生活保護基準を下まわらないよう設定されるとともに、財産課税においては最低生活を維持するために必要な土地建物等に対する課税が行われないように措置されなければなりません。

 課税最低限は、少なくとも2年に一度、物価その他のすべての事情を考慮して引き上げられることとします。 課税最低限は、少なくとも2年に一度、物価その他のすべての事情を考慮して引き上げられることとします。
 |
| 3. |
 税金は、公平に負担すべきものです。この負担公平の原則は、所得の低い者は低い割合で、所得の高い者は高い割合で負担することを意味します。したがって、この原則に反する税制上の措置は廃止されなければなりません。 税金は、公平に負担すべきものです。この負担公平の原則は、所得の低い者は低い割合で、所得の高い者は高い割合で負担することを意味します。したがって、この原則に反する税制上の措置は廃止されなければなりません。
 |
| 4. |
 納税者は、すべて個人として、または団体として関係機関に対して財政、税制、税務行政に対して意見を述べることができます。その意見は、関係機関において最大限に尊重され、立法、行政に反映させるよう努めなければなりません。 納税者は、すべて個人として、または団体として関係機関に対して財政、税制、税務行政に対して意見を述べることができます。その意見は、関係機関において最大限に尊重され、立法、行政に反映させるよう努めなければなりません。
 この規定を実効あるものにするため、政府は、租税に関する統計、税務行政や不服申立て、税務訴訟等についての詳細な情報を、毎年定期的に公表します。納税者は、実費を支払ってこれらの情報資料を入手することができます。 この規定を実効あるものにするため、政府は、租税に関する統計、税務行政や不服申立て、税務訴訟等についての詳細な情報を、毎年定期的に公表します。納税者は、実費を支払ってこれらの情報資料を入手することができます。
 |
| 5. |
 納税者は、税務行政庁の行う行為について適正手続による丁重な取扱いを受ける権利があります。適正手続の具体的内容については別に定めます。 納税者は、税務行政庁の行う行為について適正手続による丁重な取扱いを受ける権利があります。適正手続の具体的内容については別に定めます。
 |
| 6. |
 納税者は、税務行政庁が保有する自己についてのすべての情報を開示させる権利があります。その情報に誤りがある場合はこれを訂正させ、税務に関係のない情報についてはこれを消除させることができます。 納税者は、税務行政庁が保有する自己についてのすべての情報を開示させる権利があります。その情報に誤りがある場合はこれを訂正させ、税務に関係のない情報についてはこれを消除させることができます。
 |
| 7. |
 納税者は、不誠実であるという具体的な証拠がないかぎり、すべて善良な納税者として取り扱われます。 納税者は、不誠実であるという具体的な証拠がないかぎり、すべて善良な納税者として取り扱われます。
 |
| 8. |
 納税者は、税務行政上、違法・不当な処分(処分に至らないような事実上の行為を含みます。)を受けた場合には、独立した第三者機関で公正な権利救済を受けることができます。権利救済制度の具体的なあり方については別に定めます。 納税者は、税務行政上、違法・不当な処分(処分に至らないような事実上の行為を含みます。)を受けた場合には、独立した第三者機関で公正な権利救済を受けることができます。権利救済制度の具体的なあり方については別に定めます。
 |
| 9. |
 納税者は、つねに法律に定められた範囲で税負担を最少にする権利があります。税務行政庁は、納税者がこの権利を行使できるよう、たえず必要な情報を提供しなければなりません。 納税者は、つねに法律に定められた範囲で税負担を最少にする権利があります。税務行政庁は、納税者がこの権利を行使できるよう、たえず必要な情報を提供しなければなりません。
 納税者が誤った選択により過大な税負担をしていることが判明したときは、税務行政庁はすみやかに減額更正をして過納税額を納税者に還付しなければなりません。 納税者が誤った選択により過大な税負担をしていることが判明したときは、税務行政庁はすみやかに減額更正をして過納税額を納税者に還付しなければなりません。
 |
| 10. |
 給与所得者を含めて、すべての納税者は自ら所得を申告し納付すべき税額を決定する権利があります。 給与所得者を含めて、すべての納税者は自ら所得を申告し納付すべき税額を決定する権利があります。
 給与所得者は、必要経費の概算控除としての給与所得控除と実額経費控除の選択、および年末調整を受けるか確定申告をするかの選択をする権利があります。 給与所得者は、必要経費の概算控除としての給与所得控除と実額経費控除の選択、および年末調整を受けるか確定申告をするかの選択をする権利があります。
 給与所得者の実額経費控除制度については、必要経費の範囲を大幅に拡大して給与所得者に実額経費控除を選択する利益があるものに改めます。 給与所得者の実額経費控除制度については、必要経費の範囲を大幅に拡大して給与所得者に実額経費控除を選択する利益があるものに改めます。
 |
| 11. |
 納税者は、税務職員がこの憲章、憲法、各個別税法その他の法令に定められた納税者の権利を侵害していると判断したときは、何時でもその税務職員の所属する税務行政庁の長または別に定める税金オンブズマンに対してその事実を申し立て、厳正な処分を求めることができます。 納税者は、税務職員がこの憲章、憲法、各個別税法その他の法令に定められた納税者の権利を侵害していると判断したときは、何時でもその税務職員の所属する税務行政庁の長または別に定める税金オンブズマンに対してその事実を申し立て、厳正な処分を求めることができます。
 |
| 12. |
 納税者は、課税関係が生ずる取引を行おうとする場合、事前に関係税務行政庁に事実関係を明示してその課税上の取り扱いについて回答を求めることができます。この事前照会を受けた税務行政庁は、合理的な期間内に文書で回答しなければなりません。この回答は、その事案について、回答した税務行政庁を拘束します。ただし、納税者から提示された資料が不完全であったり、実際に行われた取引が提示された事実関係と異なる場合はこの限りではありません。 納税者は、課税関係が生ずる取引を行おうとする場合、事前に関係税務行政庁に事実関係を明示してその課税上の取り扱いについて回答を求めることができます。この事前照会を受けた税務行政庁は、合理的な期間内に文書で回答しなければなりません。この回答は、その事案について、回答した税務行政庁を拘束します。ただし、納税者から提示された資料が不完全であったり、実際に行われた取引が提示された事実関係と異なる場合はこの限りではありません。
 |
| 13. |
 税務行政庁は、法律の解釈や行政の執行について通達を発遣したときは、すべてこれを公開しなければなりません。通達と同一の効力を持つ文書も同様とします。 税務行政庁は、法律の解釈や行政の執行について通達を発遣したときは、すべてこれを公開しなければなりません。通達と同一の効力を持つ文書も同様とします。 |
| 1. |
 納税者は、税務調査にあたっては、少なくとも10日以上前に次の事項を記載した通知を受ける権利があります。 納税者は、税務調査にあたっては、少なくとも10日以上前に次の事項を記載した通知を受ける権利があります。

(1)調査の日時
(2)調査を行う場所
(3)調査の具体的理由
(4)調査すべき課税期間
(5)調査すべき税目
(6)調査すべき帳簿書類その他の物件の範囲
(7)調査を行う期間(調査に要する日数または時問)
(8)調査を担当する税務職員の所属、職位、氏名
 |
| 2. |
 前項の調査通知を受けた納税者は、通知された日時および場所について都合が悪いときは、その変更を求めることができます。この場合、当該税務職員は納税者の申し出を尊重して協議に応じなければなりません。 前項の調査通知を受けた納税者は、通知された日時および場所について都合が悪いときは、その変更を求めることができます。この場合、当該税務職員は納税者の申し出を尊重して協議に応じなければなりません。
 双方の協議によって調査の日時、場所の折り合いがついた場合は、税務行政庁は改めて文書でその内容を納税者に通知することとします。 双方の協議によって調査の日時、場所の折り合いがついた場合は、税務行政庁は改めて文書でその内容を納税者に通知することとします。
 |
| 3. |
 納税者は、税務調査の通知とともにこの憲章によって納税者に保障されている納税者の権利について、わかりやすい文章で説明した文書を受け取る権利を持っています。この説明書が同封されていない通知書は無効なものとみなされます。 納税者は、税務調査の通知とともにこの憲章によって納税者に保障されている納税者の権利について、わかりやすい文章で説明した文書を受け取る権利を持っています。この説明書が同封されていない通知書は無効なものとみなされます。
 |
| 4. |
 税務調査を受ける義務があるのは納税者本人だけです。法人の場合は機関としての代表取締役その他の代表者とします。家族や従業員等に対して質閤するときは、納税者本人の承諾が必要です。納税者本人の承諾を得ないで納税者以外の者に対して行った質問検査は違法なものとなります。 税務調査を受ける義務があるのは納税者本人だけです。法人の場合は機関としての代表取締役その他の代表者とします。家族や従業員等に対して質閤するときは、納税者本人の承諾が必要です。納税者本人の承諾を得ないで納税者以外の者に対して行った質問検査は違法なものとなります。
 |
| 5. |
 納税者は、税務調査を受ける場合、代理人を選任することができます。納税者が代理人を選任したときは、調査は代理人を通じて行われなければなりません。この場合、税務行政庁は、本人でないという理由で調査を拒むことはできません。代理人の資格は文書によって示すものとします。 納税者は、税務調査を受ける場合、代理人を選任することができます。納税者が代理人を選任したときは、調査は代理人を通じて行われなければなりません。この場合、税務行政庁は、本人でないという理由で調査を拒むことはできません。代理人の資格は文書によって示すものとします。
 |
| 6. |
 納税者は、税務調査にあたり自分が選んだ第三者の立会いを求めることができます。税務行政庁は、納税者が第三者の立会いを求めた場合または専門家と相談したい旨の申し出をした場合には直ちに調査を中止しなければなりません。調査は、納税者の要望を満たしたうえで続行されます。 納税者は、税務調査にあたり自分が選んだ第三者の立会いを求めることができます。税務行政庁は、納税者が第三者の立会いを求めた場合または専門家と相談したい旨の申し出をした場合には直ちに調査を中止しなければなりません。調査は、納税者の要望を満たしたうえで続行されます。
 |
| 7. |
 納税者は、税務調査に際してその旨を告げて録音をとる権利があります。また、税務行政庁が録音をとった場合は、納税者は実費を支払ってそのコピーを請求することができます。 納税者は、税務調査に際してその旨を告げて録音をとる権利があります。また、税務行政庁が録音をとった場合は、納税者は実費を支払ってそのコピーを請求することができます。
 |
| 8. |
 納税者には、税務調査にあたって、帳簿書類その他の物件を税務行政庁に持ち帰られることのない権利があります。 納税者には、税務調査にあたって、帳簿書類その他の物件を税務行政庁に持ち帰られることのない権利があります。
 納税者の文書による申し出によって帳簿書類その他の物件を課税庁に持ち帰るときは、そのコピーに申し出を受けた税務職員が署名押印して納税者に交付するとともに、預かる帳簿書類その他の物件の内容、預り期間を記載した預り証をあわせて交付しなければなりません。 納税者の文書による申し出によって帳簿書類その他の物件を課税庁に持ち帰るときは、そのコピーに申し出を受けた税務職員が署名押印して納税者に交付するとともに、預かる帳簿書類その他の物件の内容、預り期間を記載した預り証をあわせて交付しなければなりません。
 上記の預り期間にかかわらず、納税者が必要なときは何時でも返却を求めることができます。 上記の預り期間にかかわらず、納税者が必要なときは何時でも返却を求めることができます。
 |
| 9. |
 納税者は、同一の課税期間について2回以上調査を受けることはありません。もし、新しい資料に基づいて再度調査をしようとするときは、税務行政庁は、その証拠を納税者に示して協力を求めなければなりません。そのような手続を経ない重複した調査は違法な調査となります。 納税者は、同一の課税期間について2回以上調査を受けることはありません。もし、新しい資料に基づいて再度調査をしようとするときは、税務行政庁は、その証拠を納税者に示して協力を求めなければなりません。そのような手続を経ない重複した調査は違法な調査となります。
 |
| 10. |
 納税者は、税務調査を早期に終結させるよう求めることができます。特別な理由がなく3か月以上にわたった場合は、調査は終了したものとみなされ、課税処分は行われません。 納税者は、税務調査を早期に終結させるよう求めることができます。特別な理由がなく3か月以上にわたった場合は、調査は終了したものとみなされ、課税処分は行われません。
 |
| 11. |
 納税者は、税務調査が終了した場合は、文書によりその旨の通知を受けます。 納税者は、税務調査が終了した場合は、文書によりその旨の通知を受けます。 |
| 1. |
 更正等の課税処分を行うには、賦課課税方式により納付すべき税額が確定する税目以外のすべての税目について、単なる計算上の誤りを改めるような場合を除いて、適法な税務調査を経なければなりません。 更正等の課税処分を行うには、賦課課税方式により納付すべき税額が確定する税目以外のすべての税目について、単なる計算上の誤りを改めるような場合を除いて、適法な税務調査を経なければなりません。
 |
| 2. |
 更正等の課税処分を行うにあたっては、税務調査によって収集された証拠資料を示して、予め納税者に理由を明示し、これに対する反論の機会を与えなければなりません。この場合、税務行政庁は、納税者から要求があった場合は、その証拠資料のコピーを交付しなければなりません。 更正等の課税処分を行うにあたっては、税務調査によって収集された証拠資料を示して、予め納税者に理由を明示し、これに対する反論の機会を与えなければなりません。この場合、税務行政庁は、納税者から要求があった場合は、その証拠資料のコピーを交付しなければなりません。
 納税者は、更正処分が行われる前に予めこれに対して自己に有利な資料を示して反論することができます。 納税者は、更正処分が行われる前に予めこれに対して自己に有利な資料を示して反論することができます。
 |
| 3. |
 税務行政庁は、納税者に修正申告書の提出を勧奨または強要することはできません。修正申告の提出は、納税者の自発的な意思によって行われるものですから、税務行政庁の勧奨や強要にもとづいて提出された修正申告書は無効なものとします。 税務行政庁は、納税者に修正申告書の提出を勧奨または強要することはできません。修正申告の提出は、納税者の自発的な意思によって行われるものですから、税務行政庁の勧奨や強要にもとづいて提出された修正申告書は無効なものとします。
 |
| 4. |
 納税者は、税務行政庁が提示した調査結果が正当であると認めたときは、その結果に基づいて修正申告書を提出することができます。修正申告書の提出によって税務調査は終了します。この場合、修正申告書の提出は、爾後の不服申立ての権利を失うものであることを教示する義務があります。 納税者は、税務行政庁が提示した調査結果が正当であると認めたときは、その結果に基づいて修正申告書を提出することができます。修正申告書の提出によって税務調査は終了します。この場合、修正申告書の提出は、爾後の不服申立ての権利を失うものであることを教示する義務があります。
 |
| 5. |
 納税者が更正処分、決定処分または加算税等の賦課決定処分を受ける場合は、更正等の通知書で調査結果ならびに処分の具体的理由を明示される権利があります。 納税者が更正処分、決定処分または加算税等の賦課決定処分を受ける場合は、更正等の通知書で調査結果ならびに処分の具体的理由を明示される権利があります。
 更正処分によって納付すべき税額が確定するものではありません。更正処分を受けた納税者は、別に定める手続によって一定期間内に訴を提起するか不服申立てをするかを選択して更正処分等を争うことができます。更正処分等を争う方法については更正等の通知書に記載されなければなりません。 更正処分によって納付すべき税額が確定するものではありません。更正処分を受けた納税者は、別に定める手続によって一定期間内に訴を提起するか不服申立てをするかを選択して更正処分等を争うことができます。更正処分等を争う方法については更正等の通知書に記載されなければなりません。
 |
| 6. |
 納税者は、実額を把握できる資料が存在しない場合を除いて推計による課税処分を受けることはありません。推計は、直接資料がない部分にかぎって行うことができるものであり、直接資料がある部分については実額に基づいて収入金額(または益金の額)や必要経費(または損金の額)を計算しなければ違法な推計課税となります。 納税者は、実額を把握できる資料が存在しない場合を除いて推計による課税処分を受けることはありません。推計は、直接資料がない部分にかぎって行うことができるものであり、直接資料がある部分については実額に基づいて収入金額(または益金の額)や必要経費(または損金の額)を計算しなければ違法な推計課税となります。
 推計による課税処分は、その対象となる納税者の実態に基づいて行うべきものであって、類似同業者の所得率や経費率によってすることは許されません。 推計による課税処分は、その対象となる納税者の実態に基づいて行うべきものであって、類似同業者の所得率や経費率によってすることは許されません。 |