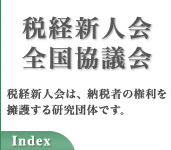
| 法人実効税率のごまかしと法人所得課税 政府税調答申、経団連提言を斬る |
| (1)「グローバル化」(グローバリゼーション)とは何か? |
貿易や資本移動に加えて、多国籍企業による国際分業をグローバリゼーションの一つの形態としてあげたのです。1990年代以降、急速にグローバル経済化が進んできていますが、その最大の特徴は、多国籍企業中心の国際分業体制が全面化している点にあります。こうしたグローバル経済化は、先進各国の新自由主義的政策の追求とともに、IMFやWTOなどの国際経済機関によっても推進されています(注 |
| (2)新自由主義の税制改革 |
| (イ)その始まりと実態 |
| (ロ)イギリスの税制改革(サッチャー) |
○サッチャー改革の全体の特徴 ○サッチャーの税制改革 (1979年改革)所得税から消費税へのシフト (1984年改革) (1988年改革) (1990年改革) ○サッチャー後の税制改革(所得課税から消費課税へのシフトを継続) メジャー内閣 ブレア内閣 (注 |
| (ハ)日本の税制改革の実態 |
(図![]() )
)
< 参考 > 最近約20年間の主な税制の変化
| 年 | 消費税 | 所得税 | 法人税 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 1986 |
||||
| 1987 | ▲最高税率→60% ○配偶者特別控除創設 |
▲基本税率→42% | ||
| 1989 | ●消費税創設 |
○基礎控除→35万円 ▲最高税率→50% ○特定扶養控除創設 |
▲基本税率→40% | |
| 1990 | ○非課税範囲の拡大 | ▲基本税率→37.5% | ||
| 1995 | ○基礎控除→38万円 ○特別減税(95・96年) |
|||
| 1997 | ●税率→5% | ●特別減税打ち切り | ||
| 1998 | ○定額減税を実施 | ▲基本税率→34.5% | ▲地価税の課税停止 | |
| 1999 | ▲最高税率→37% ○定額減税を導入 ○年少扶養控除創設 |
▲基本税率→30% | ▲有価証券取引税廃止 | |
| 2000 | ●年少扶養控除廃止 | |||
| 2002 | ▲連結納税制度導入 | |||
| 2003 | ▲証券優遇税制の導入 | ▲研究開発・IT減税 | ▲相続税減税 ●発泡酒など増税 ●たばこ税増税 |
|
| 2004 | ●免税点引下げ | ●配偶者特別控除廃止 | ||
| 2005 | ●公的年金等控除縮小 ●老年者控除廃止 |
|||
| 2006 | ●定率減税半減 | ●第3のビール増税 ●たばこ税増税 |
||
| 2007 | ●定率減税廃止 ▲証券優遇課税制の延長 |
▲減価償却制度見直し |
| 注) | ○は庶民への減税、●は庶民への増税、▲は大企業・大資産家への減税 この表のほか、07年度には、源泉移譲にともなう所得税の税率変更が実施されている |
| (第一経理ニュース08年1月号より) | |
多国籍企業は「国民経済」のワクを超えて、全世界所得、最大限の利益を追求しています。「大企業が国際競争力をつければ、輸出が増えて、日本経済が良くなり、やがて国民にもその恩恵が回ってくる」(竹中元経済財政政策担当大臣)といわれました。しかしこれは、「構造改革」を経験した多くの国民にとっては、全く日本の実情をあらわしていません。「構造改革」で利益を出しているのは大企業のみで、国民の間には貧困と格差が広がっています。史上空前の利益を上げている大企業には、法人税率引き上げによる応分の負担が必要です。定率減税の廃止や消費税増税などの庶民大増税は許されません。法人税実効税率引き下げ、消費税増税とのたたかいは、今、国民的な大きな課題になっています。 |
| (すが・たかのり) |
| (注 |
増田正人「グローバリゼーションとアメリカ経済」(「経済」08年1月) |
| (注 |
|
| (注 |
|
| (注 |
|
| (注 |
合田寛「サッチャリズムが残した「負の遺産」と税制改革」(「税制研究」NO 50) |
| (注 |
水野和夫「人はなぜグローバル経済の本質を見誤るのか」日本経済新聞社刊。 |
| ▲上に戻る |