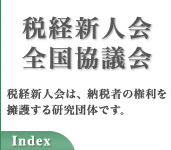|
|
|

質問0506−04【相続時精算課税後の財産分与について】

 この度、子供のいない熟年夫婦(夫A59才、妻B52才)が離婚することになりました。今現在の住居は夫Aの父親甲名義のマンションです。甲は長年開業医をしておりかなりの資産があります。甲の妻乙はすでに他界し、甲も90才を過ぎています。 この度、子供のいない熟年夫婦(夫A59才、妻B52才)が離婚することになりました。今現在の住居は夫Aの父親甲名義のマンションです。甲は長年開業医をしておりかなりの資産があります。甲の妻乙はすでに他界し、甲も90才を過ぎています。
 甲が亡くなった場合、一人息子Aの相続税の負担はかなり高額になると考えられます。 甲が亡くなった場合、一人息子Aの相続税の負担はかなり高額になると考えられます。

 そこで、相続時精算課税の3,500万円を使って、Aが家を建て、その家を妻Bに財産分与として譲渡しようと考えていますが、このような形で相続時精算課税の3,500万円の特例を使うことに何か問題はないでしょうか? そこで、相続時精算課税の3,500万円を使って、Aが家を建て、その家を妻Bに財産分与として譲渡しようと考えていますが、このような形で相続時精算課税の3,500万円の特例を使うことに何か問題はないでしょうか?

 上記の場合、住宅取得が要件ですから、一時、居住し、その後財産分与という運びを検討していますが、最低どの程度の期間、居住していれば認められるものなのでしょうか? 上記の場合、住宅取得が要件ですから、一時、居住し、その後財産分与という運びを検討していますが、最低どの程度の期間、居住していれば認められるものなのでしょうか?

 そもそも離婚の場合の財産分与ですが、夫婦二人で築いた財産がないのに財産分与というのはあり得るでしょうか? そもそも離婚の場合の財産分与ですが、夫婦二人で築いた財産がないのに財産分与というのはあり得るでしょうか? |
| 回答0506−04【相続時精算課税後の財産分与について】 |
大阪会 疋田 疋田 英司 英司 |


 財産分与の意義は 財産分与の意義は 夫婦財産の精算、 夫婦財産の精算、 離婚後の扶養、 離婚後の扶養、 損害賠償の3点です。 損害賠償の3点です。

 その判断の基準としては、当事者の寄与の程度、婚姻期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、年齢、心身の状況、職業等を勘案して判断されます。そういう点で、将来、夫が支給される予定の退職金や年金への寄与なども考慮の範囲とされています。性別役割分業の結果、就労機会につけなかった妻の生活保障を離婚後もみるのは当然という考え方です。 その判断の基準としては、当事者の寄与の程度、婚姻期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、年齢、心身の状況、職業等を勘案して判断されます。そういう点で、将来、夫が支給される予定の退職金や年金への寄与なども考慮の範囲とされています。性別役割分業の結果、就労機会につけなかった妻の生活保障を離婚後もみるのは当然という考え方です。

 本件の場合、詳細は不明ですが、妻は結婚により就労機会がなかったため職業能力が身に備わっていない原因が、専業主婦という性別役割分業の結果だとすれば、離婚後の生活補助を夫が持つという理由になります。さらに、夫に不貞の行為があるなど、妻に対する精神的苦痛を与えたとすれば慰謝料が加算されます。 本件の場合、詳細は不明ですが、妻は結婚により就労機会がなかったため職業能力が身に備わっていない原因が、専業主婦という性別役割分業の結果だとすれば、離婚後の生活補助を夫が持つという理由になります。さらに、夫に不貞の行為があるなど、妻に対する精神的苦痛を与えたとすれば慰謝料が加算されます。

 ということで、夫婦で築いた財産がない場合でも、財産分与がされます。ご質問のような疑問がでるのはネーミングからくる印象のせいだと思います。 ということで、夫婦で築いた財産がない場合でも、財産分与がされます。ご質問のような疑問がでるのはネーミングからくる印象のせいだと思います。

 税務上の取扱いでは相続税基本通達9−8(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)がその取扱いを定めています。同通達は以下のとおり定めています。 税務上の取扱いでは相続税基本通達9−8(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)がその取扱いを定めています。同通達は以下のとおり定めています。

 「婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条〔財産分与〕、第771条〔協議上の離婚の規定の準用〕及び第749条〔離婚の規定の準用〕参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。」 「婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条〔財産分与〕、第771条〔協議上の離婚の規定の準用〕及び第749条〔離婚の規定の準用〕参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。」

 ただし書きのように、あまりに過大な財産分与に対しては贈与税の課税をしますとあります。どの判例だったか覚えていませんが、実際にこのような事例はあって、大企業の社長が偽装離婚して数億円の財産を分与した例がありましたが、結果的に贈与税が課税されたケースはあります。一方、最近の裁判では債権者から財産を守るために離婚して妻の本来持分を贈与したことが債権者に対する詐害行為として訴訟になったケースがありましたが、それにあたらないとする判決も出ています。 ただし書きのように、あまりに過大な財産分与に対しては贈与税の課税をしますとあります。どの判例だったか覚えていませんが、実際にこのような事例はあって、大企業の社長が偽装離婚して数億円の財産を分与した例がありましたが、結果的に贈与税が課税されたケースはあります。一方、最近の裁判では債権者から財産を守るために離婚して妻の本来持分を贈与したことが債権者に対する詐害行為として訴訟になったケースがありましたが、それにあたらないとする判決も出ています。

 なお、分与した側の課税については所得税基本通達33−1の4(財産分与による資産の移転)という取扱いがあり、以下のとおり定めています。 なお、分与した側の課税については所得税基本通達33−1の4(財産分与による資産の移転)という取扱いがあり、以下のとおり定めています。

 民法第768条《財産分与の請求》(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。 民法第768条《財産分与の請求》(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。 |

| (注)1 |
 財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡であり、贈与ではないから、法第59条第1項《みなし譲渡課税》の規定は適用されない。 財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡であり、贈与ではないから、法第59条第1項《みなし譲渡課税》の規定は適用されない。 |
| 2 |
 財産分与により取得した資産の取得費については、38−6参照 財産分与により取得した資産の取得費については、38−6参照 |

 以上の通達を元に、譲渡所得の計算をします。なお、居住用財産を譲渡した場合の特例(租税特別措置法第35条)は、親族への譲渡の場合は認めていませんが、離婚後は他人なので特例が認められます。 以上の通達を元に、譲渡所得の計算をします。なお、居住用財産を譲渡した場合の特例(租税特別措置法第35条)は、親族への譲渡の場合は認めていませんが、離婚後は他人なので特例が認められます。

 離婚調停前に名義を代える場合、贈与税の配偶者控除を使うというケースも聞かれますが、税務署の現場実務では実質的に婚姻関係がないのであれば、財産分与と認めるケースがあります。事実認定の問題なので、実質的に別居し、離婚調停中だったりすれば、婚姻中の場合でも財産分与と認定する場合もあります。この場合は事前に税務署で事実関係を説明して確認しておくほうがよいでしょう。 離婚調停前に名義を代える場合、贈与税の配偶者控除を使うというケースも聞かれますが、税務署の現場実務では実質的に婚姻関係がないのであれば、財産分与と認めるケースがあります。事実認定の問題なので、実質的に別居し、離婚調停中だったりすれば、婚姻中の場合でも財産分与と認定する場合もあります。この場合は事前に税務署で事実関係を説明して確認しておくほうがよいでしょう。 |

 相続時精算課税の特例は、相続税法第21条の9に規定され、贈与者・受贈者の年齢制限をしています。この特例として住宅取得資金の贈与の場合、租税特別措置法第70条の3(特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)は贈与者が65歳未満の者が住宅取得資金を贈与した場合でも相続時精算課税制度の適用を認めるとする特例です。 相続時精算課税の特例は、相続税法第21条の9に規定され、贈与者・受贈者の年齢制限をしています。この特例として住宅取得資金の贈与の場合、租税特別措置法第70条の3(特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)は贈与者が65歳未満の者が住宅取得資金を贈与した場合でも相続時精算課税制度の適用を認めるとする特例です。

さらに租税特別措置法第70条の3の2(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税にかかる贈与税の特別控除の特例)で、住宅取得資金の贈与がある場合は住宅取得特別控除1,000万円の控除を加算する特例です。つまり、この3つの法令の組み合わせで住宅取得資金贈与の特例が構成されています。

 ご質問の問題点は、贈与者は90歳、受贈者は59歳と相続税法第21条の9の各規定はクリアしているわけですから、2500万円までの控除は使えます。 ご質問の問題点は、贈与者は90歳、受贈者は59歳と相続税法第21条の9の各規定はクリアしているわけですから、2500万円までの控除は使えます。
 問題は措置法第70条の3の2の1,000万円の特別が使えるかどうかに絞られます。 問題は措置法第70条の3の2の1,000万円の特別が使えるかどうかに絞られます。

 この特例の基準は租法第70条の3を引用しています。 この特例の基準は租法第70条の3を引用しています。

 第一に、措置法第70条の3第1項第1〜3号に特定受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築または中古住宅の購入、増改築して居住の用に供している場合または確実に供すると見込まれる場合には特例を認めるとしています。3月15日までということは、それまで居住の用に供すればよいとなります。 第一に、措置法第70条の3第1項第1〜3号に特定受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築または中古住宅の購入、増改築して居住の用に供している場合または確実に供すると見込まれる場合には特例を認めるとしています。3月15日までということは、それまで居住の用に供すればよいとなります。

 第二に、同条第4項には、第一の基準にある居住が確実と見込まれる場合で、その年の年末までに居住できなかった場合は、特例を認めないという規定です。今回の判断には直接関係ありません。 第二に、同条第4項には、第一の基準にある居住が確実と見込まれる場合で、その年の年末までに居住できなかった場合は、特例を認めないという規定です。今回の判断には直接関係ありません。
 贈与年の翌年3月15日までの居住開始が一つの基準として示されています。 贈与年の翌年3月15日までの居住開始が一つの基準として示されています。

 本件の場合、受贈者本人が居住の用に供する目的がないと思われますので、特例そのもの対象外であると思われます。したがって、2500万円の控除を使い、超過分は20%の税率を適用して相続時精算課税適用の贈与税申告となります。 本件の場合、受贈者本人が居住の用に供する目的がないと思われますので、特例そのもの対象外であると思われます。したがって、2500万円の控除を使い、超過分は20%の税率を適用して相続時精算課税適用の贈与税申告となります。

 一方、贈与年に居住した事実があって、年の途中で財産分与をした場合はどうかという点について、類似の質疑が国税庁の質疑応答事例集にあります。贈与年の中途に出国し、3月15日時点では居住していないケースの場合の特例適用可否の考え方が載っています。これによれば、居住の用に供したかどうかは、その者の生活の拠点として利用したかどうかで判断すべきとしています。では、一度でも拠点にすればよいのかというと、住宅用家屋の購入時において、 一方、贈与年に居住した事実があって、年の途中で財産分与をした場合はどうかという点について、類似の質疑が国税庁の質疑応答事例集にあります。贈与年の中途に出国し、3月15日時点では居住していないケースの場合の特例適用可否の考え方が載っています。これによれば、居住の用に供したかどうかは、その者の生活の拠点として利用したかどうかで判断すべきとしています。では、一度でも拠点にすればよいのかというと、住宅用家屋の購入時において、 海外転勤が予定されておらず、 海外転勤が予定されておらず、 予定されていても帰国後は居住する予定であることが認められるのであればOKとあります。この場合、海外移転に伴い譲渡した場合でも前述の条件 予定されていても帰国後は居住する予定であることが認められるのであればOKとあります。この場合、海外移転に伴い譲渡した場合でも前述の条件 を満たしていれば特例適用は可との窓口回答もあります。ただし、この窓口回答は担当者個人の感触のようなので、具体的には事前の相談が必要と思われます。 を満たしていれば特例適用は可との窓口回答もあります。ただし、この窓口回答は担当者個人の感触のようなので、具体的には事前の相談が必要と思われます。

 譲渡一般で見た場合、住宅を取得した後、例えば収用の申し出があって譲渡せざるを得ない場合などは、居住の用に供したと判断するところでしょう。しかし、本件の場合、財産分与が住宅取得後に発生し、贈与年中に移転することなど一般的には考えにくい面がありますので特例の適用については税務当局として認めがたい面もあると思われます。もちろん、家が建ってから三下り半を突きつけられる夫もないとも限りませんが。 譲渡一般で見た場合、住宅を取得した後、例えば収用の申し出があって譲渡せざるを得ない場合などは、居住の用に供したと判断するところでしょう。しかし、本件の場合、財産分与が住宅取得後に発生し、贈与年中に移転することなど一般的には考えにくい面がありますので特例の適用については税務当局として認めがたい面もあると思われます。もちろん、家が建ってから三下り半を突きつけられる夫もないとも限りませんが。

 なお、相続税の小規模宅地特例のように、申告期限まで保有する要件はこの特例にはありません。したがって3月15日まで保有していなかったことをもって特例の対象外とする基準はありません。問題は特例趣旨に合致するかどうかです。 なお、相続税の小規模宅地特例のように、申告期限まで保有する要件はこの特例にはありません。したがって3月15日まで保有していなかったことをもって特例の対象外とする基準はありません。問題は特例趣旨に合致するかどうかです。
 まとめてみますと、相続時精算課税で贈与した財産で財産分与を行っても、その価格が相当であれば財産分与と認められます。 まとめてみますと、相続時精算課税で贈与した財産で財産分与を行っても、その価格が相当であれば財産分与と認められます。
 相続時精算課税により贈与税の申告。住宅取得資金贈与の特例は不可です。 相続時精算課税により贈与税の申告。住宅取得資金贈与の特例は不可です。
 財産分与で受けた側は過大な財産でなければ申告は不要です。 財産分与で受けた側は過大な財産でなければ申告は不要です。
 財産分与で送った側は、譲渡所得の申告をしますが、居住用でないため措置法35条は使えません。しかし、原価は建築直後に分与したので建物は譲渡所得は発生しません。土地の贈与があったとすれば、その取得時期を引き継ぎますので、概算取得費控除を利用する場合は譲渡所得が発生するケースがあります。 財産分与で送った側は、譲渡所得の申告をしますが、居住用でないため措置法35条は使えません。しかし、原価は建築直後に分与したので建物は譲渡所得は発生しません。土地の贈与があったとすれば、その取得時期を引き継ぎますので、概算取得費控除を利用する場合は譲渡所得が発生するケースがあります。

 以上、引用も多く冗長的になりましたが、本件の課税取扱いに関わる問題点を整理しました。 以上、引用も多く冗長的になりましたが、本件の課税取扱いに関わる問題点を整理しました。 |
(ひきた・えいじ) |
 |
参考
住宅取得資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
【照会要旨】
 住宅取得資金の贈与を受け居住用不動産を取得した者が、その居住用不動産を自己の居住の用に供した後、夫の海外転勤に伴い、当該贈与を受けた年の中途で出国した場合、租税特別措置法第70条の3第1項の規定の適用がありますか。 住宅取得資金の贈与を受け居住用不動産を取得した者が、その居住用不動産を自己の居住の用に供した後、夫の海外転勤に伴い、当該贈与を受けた年の中途で出国した場合、租税特別措置法第70条の3第1項の規定の適用がありますか。

【回答要旨】
 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(措法70の3)の適用要件の一つとして、「特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに、・・・同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき」とされていますが、「居住の用に供した」かどうかは、その住宅用家屋をその者の生活の拠点として利用したかどうかにより判断すべきであると解されます。 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(措法70の3)の適用要件の一つとして、「特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに、・・・同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき」とされていますが、「居住の用に供した」かどうかは、その住宅用家屋をその者の生活の拠点として利用したかどうかにより判断すべきであると解されます。

 したがって、照会の場合、その住宅用家屋の購入契約時において、海外転勤が予定されておらず、入居時に海外転勤に伴う出国が予定されていても、その住宅用家屋が帰国後において居住予定のものであると認められるときは、この要件を満たすものと考えられます。 したがって、照会の場合、その住宅用家屋の購入契約時において、海外転勤が予定されておらず、入居時に海外転勤に伴う出国が予定されていても、その住宅用家屋が帰国後において居住予定のものであると認められるときは、この要件を満たすものと考えられます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第70条の3第1項 |
 (国税庁ホームページより引用) (国税庁ホームページより引用) |
|
|