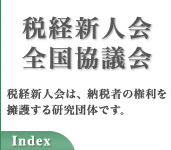| 1.法9条の解釈論 |
| (1)法9条の目的 |
 法9条は、すべての事業者を対象として、単一の基準に基づいて免税事業者を弁別することを目的とする規定である。 法9条は、すべての事業者を対象として、単一の基準に基づいて免税事業者を弁別することを目的とする規定である。
 |

 |
 法4条1項が免税事業者、課税事業者の区別なく「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する」とし、4条1項の例外である6条1項には「消費税を課さない」という文言が用いられていること、法9条1項が法6条1項と異なり、「消費税を課さない」という文言ではなく、「消費税を納める義務を免除する」という文言を用いていることから、免税事業者を含むすべての事業者の取引に消費税が課され、ただし免税事業者の場合には法9条によってその税を納める義務が免除されるにすぎないと読むのが文理解釈上自然である。 法4条1項が免税事業者、課税事業者の区別なく「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する」とし、4条1項の例外である6条1項には「消費税を課さない」という文言が用いられていること、法9条1項が法6条1項と異なり、「消費税を課さない」という文言ではなく、「消費税を納める義務を免除する」という文言を用いていることから、免税事業者を含むすべての事業者の取引に消費税が課され、ただし免税事業者の場合には法9条によってその税を納める義務が免除されるにすぎないと読むのが文理解釈上自然である。
 |

 |
 法9条1項に定める「事業者」には、基準期間において課税事業者である事業者と免税事業者である事業者の区別をすることなく双方を含んでおり、すべての事業者に103分の3を控除した金額をもって小規模事業者性を判定すると解釈するのが自然である。 法9条1項に定める「事業者」には、基準期間において課税事業者である事業者と免税事業者である事業者の区別をすることなく双方を含んでおり、すべての事業者に103分の3を控除した金額をもって小規模事業者性を判定すると解釈するのが自然である。
 |

 |
 消費税法施行からしばらくの問は,課税庁においても、このような解釈に基づいた運用を当然のごとくおこなっていた事実は、上告人の解釈の妥当性を何よりも示している。 消費税法施行からしばらくの問は,課税庁においても、このような解釈に基づいた運用を当然のごとくおこなっていた事実は、上告人の解釈の妥当性を何よりも示している。
 |
| (2)明確かつ単一な「物差し」 |
 小規模事業者への事務負担の配慮という法9条の立法趣旨からすると、小規模事業者の判定基準として最も重要なのは、争いの生じない明確な基準、可能なかぎり「明確かつ単一な物差し」であることである。 小規模事業者への事務負担の配慮という法9条の立法趣旨からすると、小規模事業者の判定基準として最も重要なのは、争いの生じない明確な基準、可能なかぎり「明確かつ単一な物差し」であることである。
 基準期間において免税・課税の区別をしない上告人の解釈は、その要請に沿うものである。 基準期間において免税・課税の区別をしない上告人の解釈は、その要請に沿うものである。
 |
| (3)法9条2項における28条1項の借用 |
 消費税の課税標準計算において税抜きで課税売上高を判定すること(28条1項)と、小規模事業者性の判定においてその規定を借用するということ(9条2項)とは、それぞれにその条項の目的が異なることから、「課されるべき消費税に相当する額」という文言の意味内容も異なってくる。課税標準の計算という性質上、課税事業者のみが対象とされる規定である28条1項を、免税事業者を含むすべての事業者を対象とする法9条2項に借用しているのであるから、そこでの「課されるべき消費税に相当する額」の意味も、小規模事業者性の判定(納税義務の有無を問わず事業規模の大小を判定するだけの)基準であるという同条の趣旨に合致した形で解釈されなくてはならない。 消費税の課税標準計算において税抜きで課税売上高を判定すること(28条1項)と、小規模事業者性の判定においてその規定を借用するということ(9条2項)とは、それぞれにその条項の目的が異なることから、「課されるべき消費税に相当する額」という文言の意味内容も異なってくる。課税標準の計算という性質上、課税事業者のみが対象とされる規定である28条1項を、免税事業者を含むすべての事業者を対象とする法9条2項に借用しているのであるから、そこでの「課されるべき消費税に相当する額」の意味も、小規模事業者性の判定(納税義務の有無を問わず事業規模の大小を判定するだけの)基準であるという同条の趣旨に合致した形で解釈されなくてはならない。

 従って、9条の趣旨からすれば、「当該基準期間において、すべての事業者が課税事業者であるとした場合において課されることになる消費税相当額」と解すべきこととなる。 従って、9条の趣旨からすれば、「当該基準期間において、すべての事業者が課税事業者であるとした場合において課されることになる消費税相当額」と解すべきこととなる。 |
 |
| 2.小規模事業者性の判定基準としての実質的妥当性 |
| (1)単一の基準 |
 課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、課税資産の譲渡等の対価の額から「103分の3」を控除した金額(=「基準期間における課税売上高」)を単一の基準とすることが、実質的・経済的観点からも妥当な解釈である。 課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、課税資産の譲渡等の対価の額から「103分の3」を控除した金額(=「基準期間における課税売上高」)を単一の基準とすることが、実質的・経済的観点からも妥当な解釈である。
 |
| (2)消費税は「預り金」ではない |
 上記の妥当性は、第一に、消費税は「預り金」ではなく「価格の一部」である(東京地裁[平成2年3月26日]判決など)ということ、第二に消費税相当額を転嫁できるか否かは、各事業者の市場の競争力によって決まるという事実からも理解できよう。 上記の妥当性は、第一に、消費税は「預り金」ではなく「価格の一部」である(東京地裁[平成2年3月26日]判決など)ということ、第二に消費税相当額を転嫁できるか否かは、各事業者の市場の競争力によって決まるという事実からも理解できよう。
 |
| (3)税制改革法11条は訓示規程 |
 税制改革法との関係を論じれば、同法11条は、消費税が適正に転嫁されるよう、事業者および国等が適切な配慮を行うべきことを定めた規定である。しかし、前述したように、消費税は「預り金」ではなく「価格の一部」であることから、同条は一種の訓示規定であって、そこから何ら法的な効果が発生するものではない。 税制改革法との関係を論じれば、同法11条は、消費税が適正に転嫁されるよう、事業者および国等が適切な配慮を行うべきことを定めた規定である。しかし、前述したように、消費税は「預り金」ではなく「価格の一部」であることから、同条は一種の訓示規定であって、そこから何ら法的な効果が発生するものではない。

 したがって、同条は、上記2(1)の解釈の妥当性に何らの影響を及ぼすものではないといえる。 したがって、同条は、上記2(1)の解釈の妥当性に何らの影響を及ぼすものではないといえる。 |
 |
| 3.本件に関する税務実務の現場の状況と多くの税理士の理解 |
| (1)課税庁も同様の判断 |
 課税庁も法施行当初は明確に上告人と同様の解釈をしていた。法人税取扱通達平成元年3月1日直法2−1は、本文において免税事業者である法人について「税込経理方式」をとるべきことを定め、同通達第5項〈免税事業者の消費税の処理〉の(注)2に「これらの法人(免税事業者)が行う取引に係る消費税の額は、・・・」としており、免税事業者の取引にも消費税が課されることを当然の前提としていた。 課税庁も法施行当初は明確に上告人と同様の解釈をしていた。法人税取扱通達平成元年3月1日直法2−1は、本文において免税事業者である法人について「税込経理方式」をとるべきことを定め、同通達第5項〈免税事業者の消費税の処理〉の(注)2に「これらの法人(免税事業者)が行う取引に係る消費税の額は、・・・」としており、免税事業者の取引にも消費税が課されることを当然の前提としていた。
 |
| (2)「税込み」「税抜き」・・・税はある |
 課税庁サイドが編集等している文献も、法9条の課税売上高については単に「税抜き」と記述しており「税抜きだが、免税事業者には税がないので・・・」との説明をしているものは存在しない。 課税庁サイドが編集等している文献も、法9条の課税売上高については単に「税抜き」と記述しており「税抜きだが、免税事業者には税がないので・・・」との説明をしているものは存在しない。

 現場税務職員も、本件調査時に解釈根拠条文が説明するたびに異なり、最終的には国税局への確認の結果として、解釈根拠条文は法9条でも28条でもなく、あえていえば税制改革法10条・11条であると説明した。しかも、この段階でも「税込み」なのか「税抜き」なのかという問題設定でのやりとりであった。 現場税務職員も、本件調査時に解釈根拠条文が説明するたびに異なり、最終的には国税局への確認の結果として、解釈根拠条文は法9条でも28条でもなく、あえていえば税制改革法10条・11条であると説明した。しかも、この段階でも「税込み」なのか「税抜き」なのかという問題設定でのやりとりであった。
 |
| (3)税務署も上告人と同様の指導 |
 税務の現場では、下記のような上告人主張どおりの指導例等が散見された。 税務の現場では、下記のような上告人主張どおりの指導例等が散見された。 |
 |
税理士が税務署との折衝、指導を受けた事例 |
 |
税務署主催の研修会での説明 |
 |
民間税務研修会での講師自らの説明 |
 |
税務申告時に、上告人の主張のとおり税務署が指導していた事例。 |